前回【前編】では、発達障がいやグレーゾーンのお子さんを育てる上で、地域の相談窓口を知っておくことのメリットや、具体的な相談先をご紹介しました。
今回は、実際に相談するときの不安や「どう話せばいいの?」という気持ちに寄り添いながら、準備のヒントや相談することの意味について、お伝えします。
準備のポイント
「うまく話せるか心配…」私もそうでした。
そんなときは、少し準備しておくと安心です。
専門職は、話を聞くプロ。
一緒に整理しながら話しを聞いてくれます。
「こうなってくれたら嬉しい」という希望や、期待するサポートを整理しておくと、相談がスムーズに進みます。
聞き忘れを防ぐために、事前にメモしておくと安心です。
母子手帳、園や学校の連絡帳、発達検査の結果などがあれば準備しましょう。
うまく話せなくても大丈夫。
「ちょっとうまく言えないんですけど…」と正直に伝えてもいいと思います。
大切なのは、困っていると感じているあなたの気持ちを伝えることです。
相談することは「自立」すること
「人に頼るのは甘えなんじゃ…」
「自分で何とかしなきゃ…」
そう思ってしまうこと、私にもありました。
でも私は今、「親の自立とは、必要なときに相談できること」だと考えています。
それは弱さではなく、自分と家族を守るための大切なセルフケアです。
一人で抱え続けると、心は疲れ、イライラしやすくなります。
そうなると、子どもの困りごとにも余裕を持って向き合うのが難しくなる場合も。
しかし、誰かに話してみるだけでも、心が軽くなり、前に進めることがあります。
脳性まひの小児科医である熊谷晋一郎さんの言葉に、「自立とは依存先を増やすこと」というものがあります。
支えてくれる人や場所を見つけることは、自立への大切な一歩です。
勇気を出して、地域の「頼れる場所」のドアをノックしてみませんか?
きっと、あなたの思いに耳を傾け、温かく迎えてくれる人がいます。

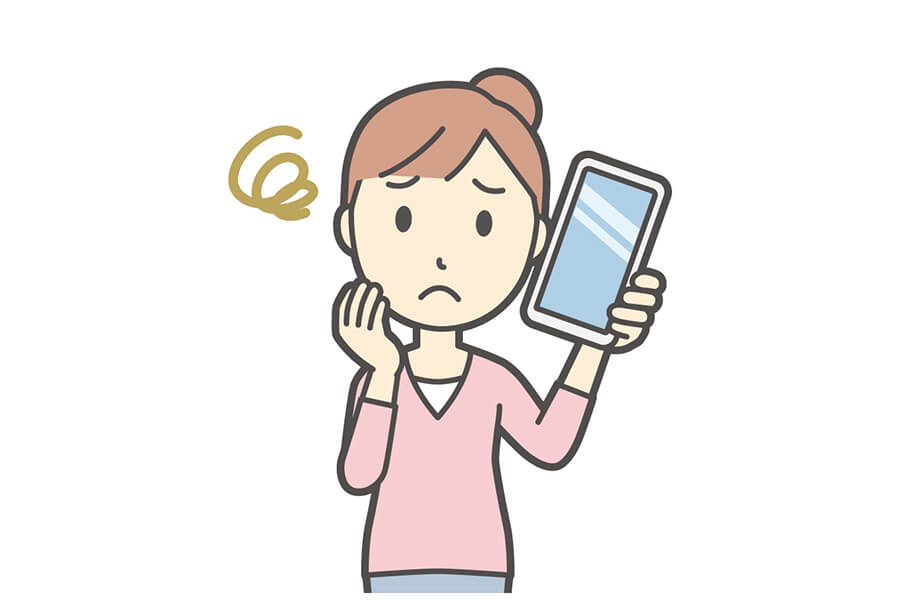



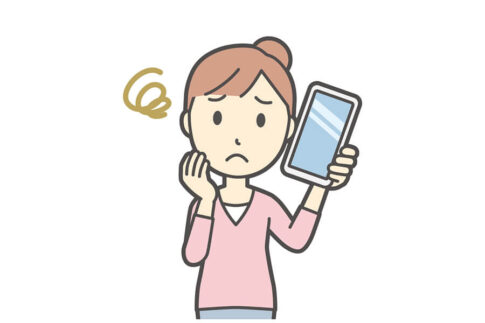
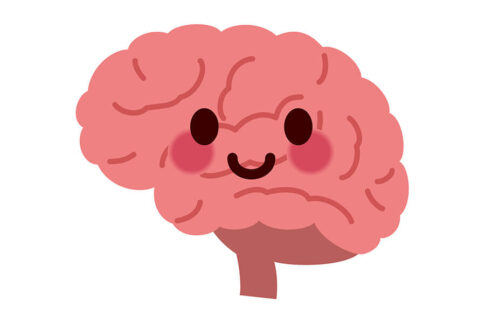


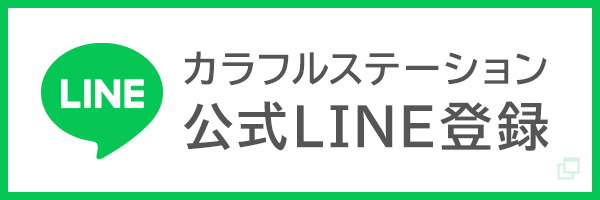
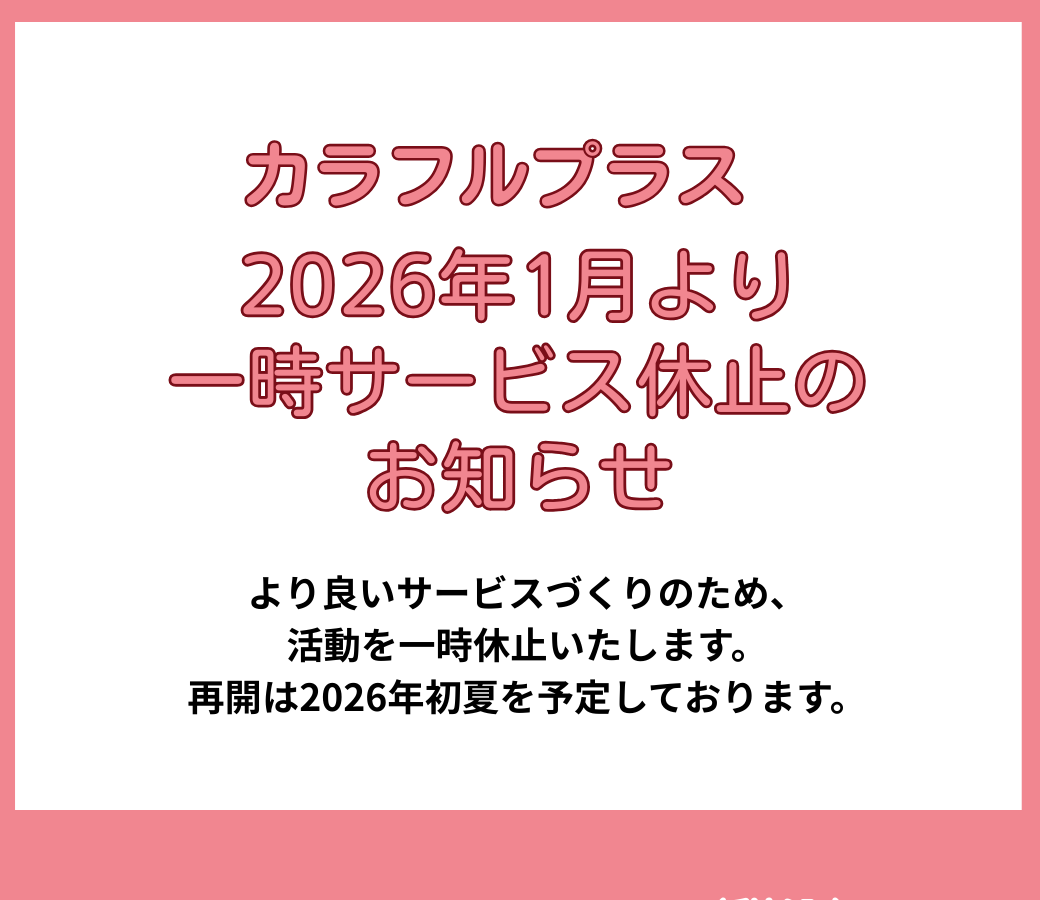





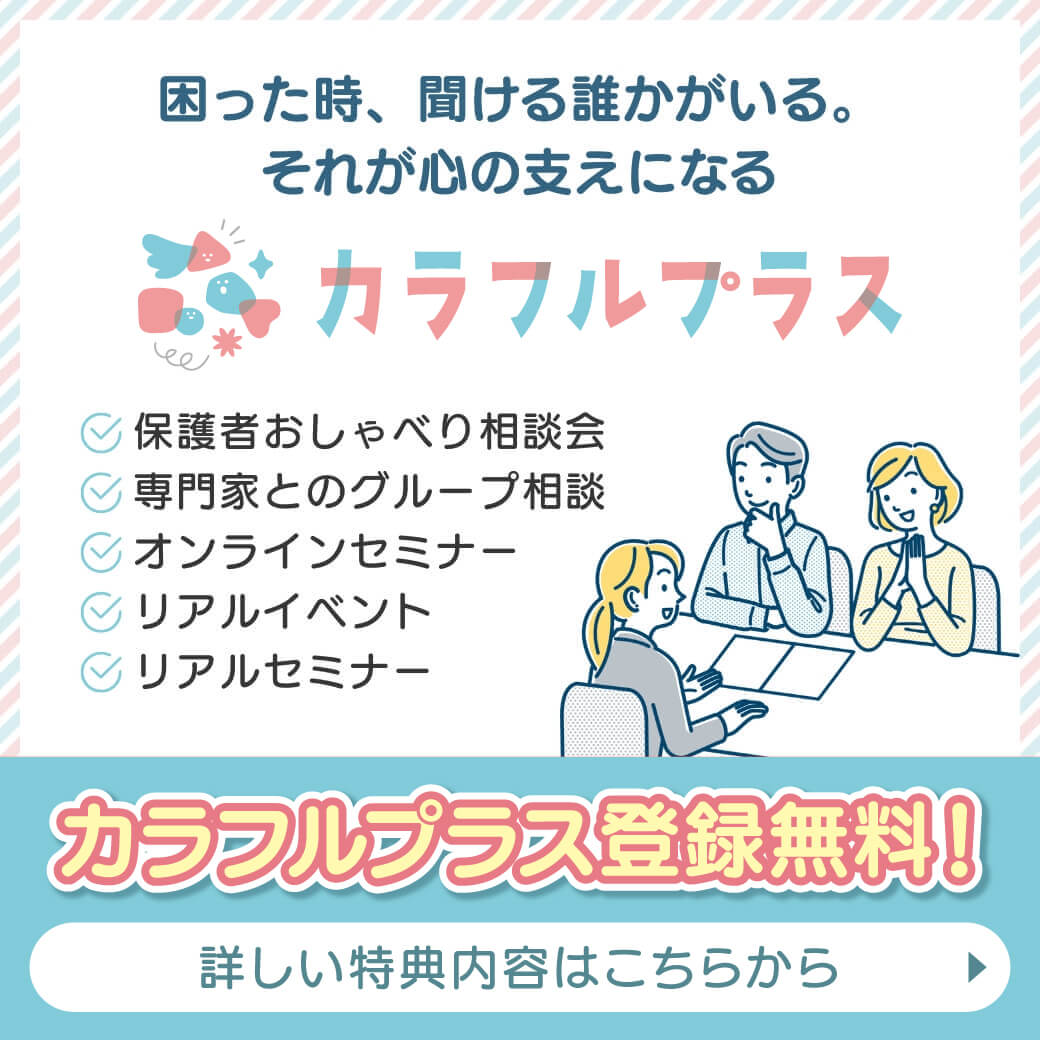
「いつ、どこで、どんな時に、どうなるか」など、お子さんの様子を箇条書きでメモしておきましょう。