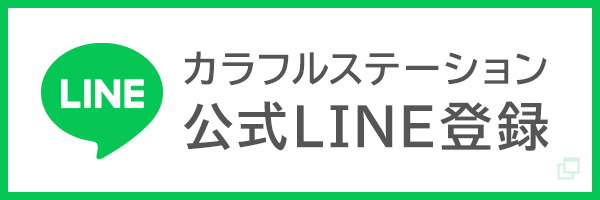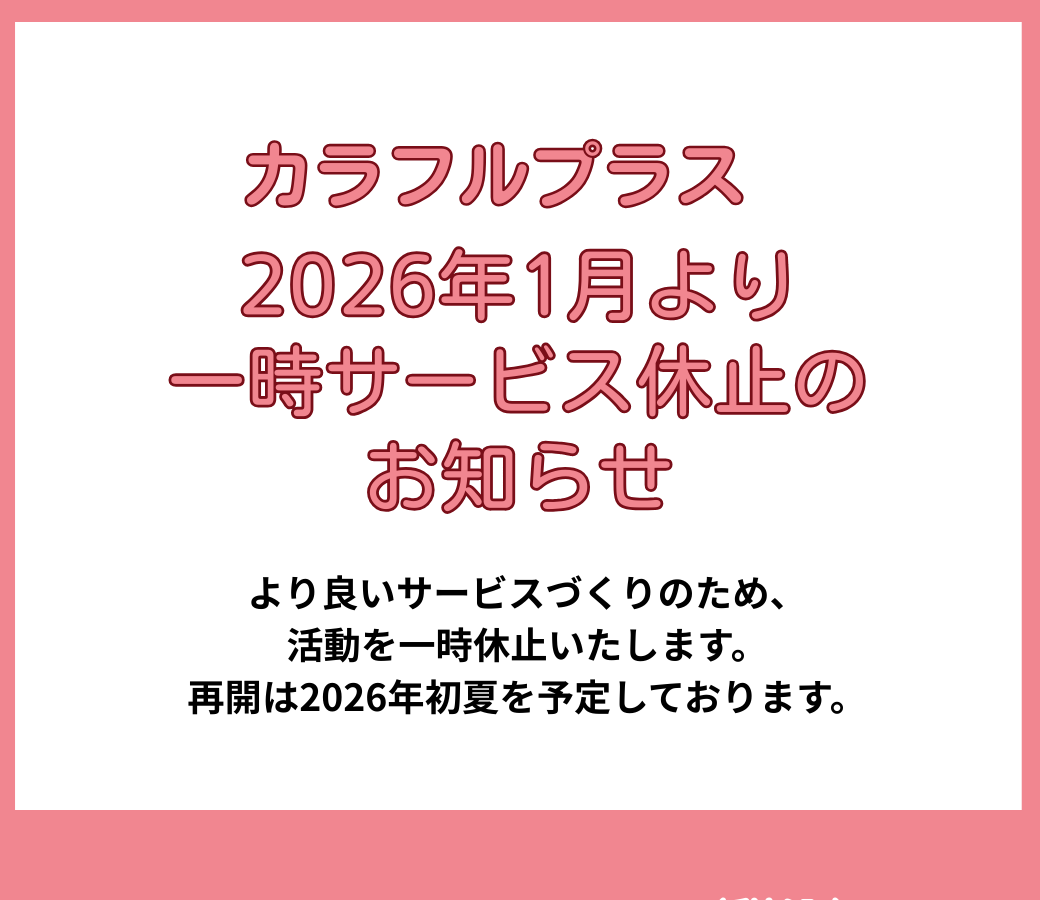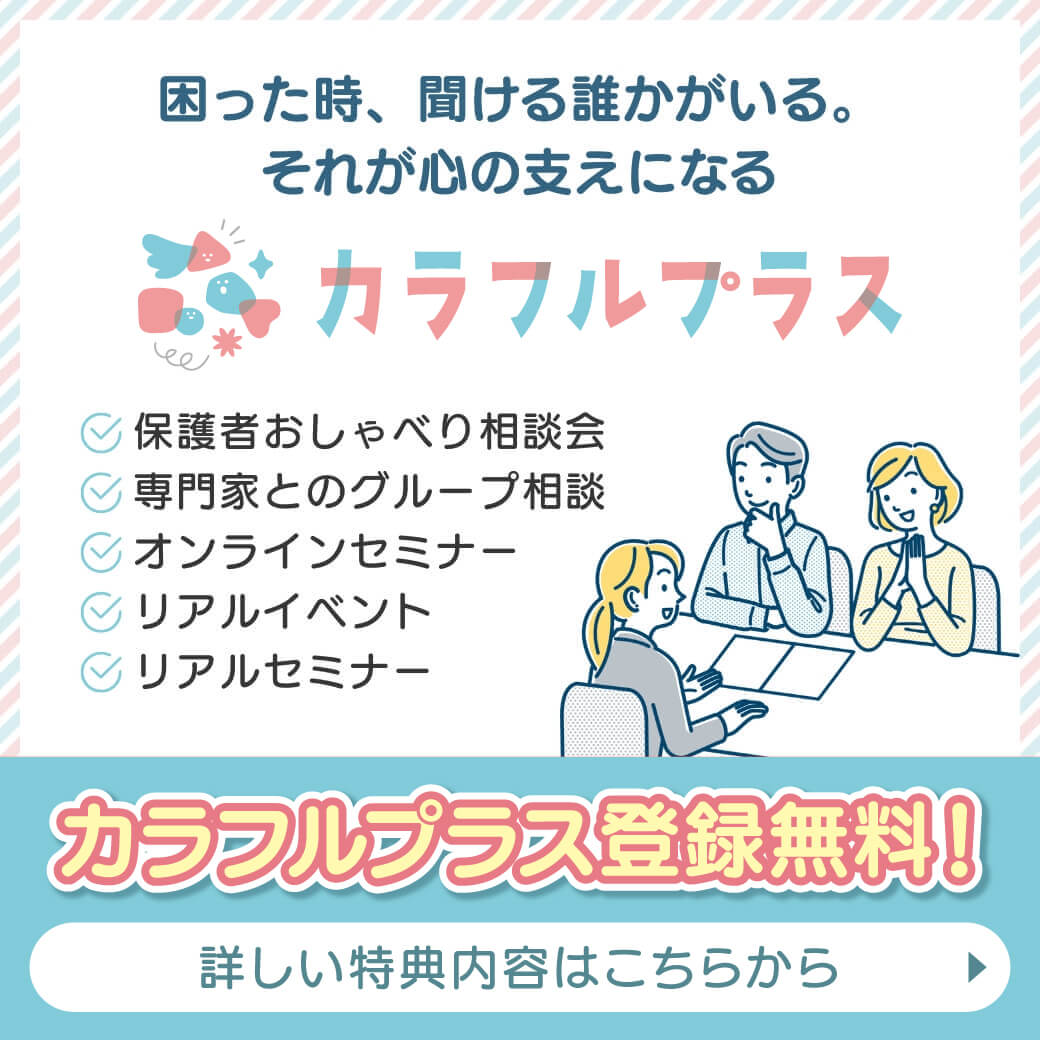「勉強は嫌いじゃないのに、なぜか読み書きや計算が苦手」
そんな悩みを抱える子どもの中には、実は学習障害(LD)の可能性がある場合があります。
学習障害は、知的発達に遅れがないにもかかわらず、「読む」「書く」「計算する」など、特定 の学習分野に困難を示す状態です。
主なタイプ
たとえば、音読が極端にたどたどしい、計算の手順が毎回あいまい、簡単な漢字でも何度も忘れてしまうといった様子がある場合、学習障害(LD)の特性があるかもしれません。
学習障害(LD)と聞くと身構えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、困難を示す特定の分野に合わせて支援や合理的配慮を行うことで、その子の困り感を軽減させることができます。
家庭でできる支援の方法
苦手を責めず、やり方を教える
・「また間違えた」ではなく、「どうすればやりやすい?」と一緒に考える姿勢が大切
・書くことが苦手なら、「口で答えてOK」「チェックで選ばせる」といった対応を
・計算が苦手なら、九九表で確認しながら進めたり、補助線などをひいたりすることで間違いを少なくする工夫を
ICTツールを活用する
・音声入力や読み上げ機能があるタブレットでの学習を取り入れる
・学習アプリを使って、特性にあった学習スタイルを見つけましょう
・無料の読み書き支援アプリ(例:UDトーク)も有効
学校での合理的配慮
・板書が難しい子には、プリント配布や写真撮影の許可を
・テストでは、選択式にする、時間を延ばす、ふりがなをつけるなどの個別支援も
・通級支援教室や支援員の活用も有効
学校と連携し、「できない」ではなく「どうすればできるか」を話し合うことが支援の土台になります。
親として大切にしたいこと
・他の子と比べるより、その子のペースを大切に
・得意なこと(絵、記憶、話す力など)を見つけて、できた!という体験を積ませる
・子どもが困ったときやできないときに、「分からなくて困ってる」と言える親子関係作り
まとめ
学習障害がある子どもたちは「努力不足」なのではなく、理解の仕方が少し違うだけ。
正しい理解と支援があれば、「わかる力」「できる力」は確実に伸びていきます。
家庭でも学校でも、「努力が足りない」ではなく、「工夫していこう」という視点をもつことが、子どもの未来を拡げる第一歩になります。