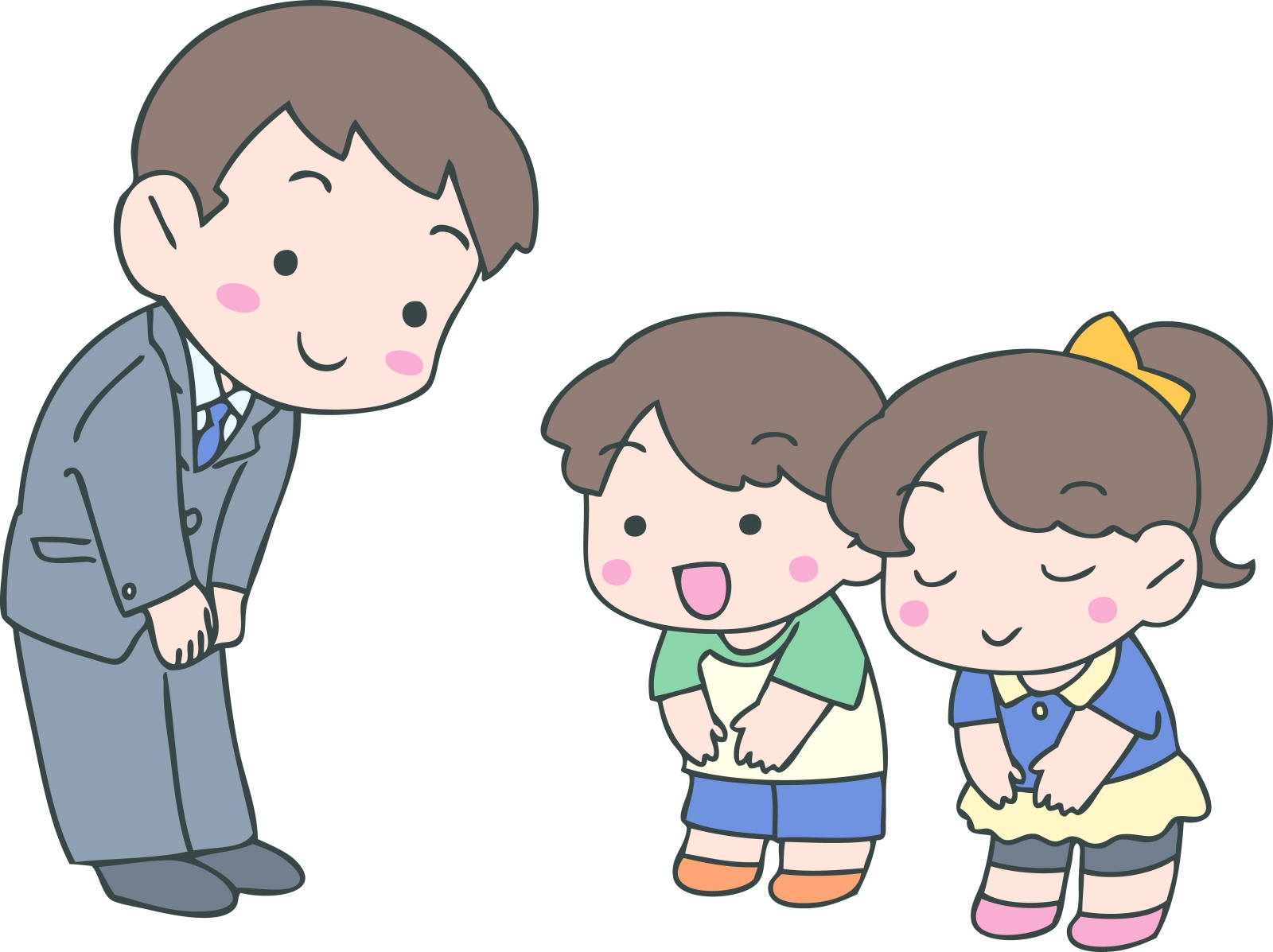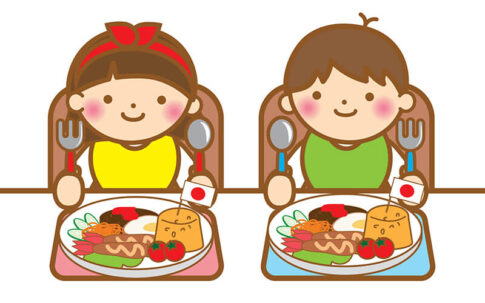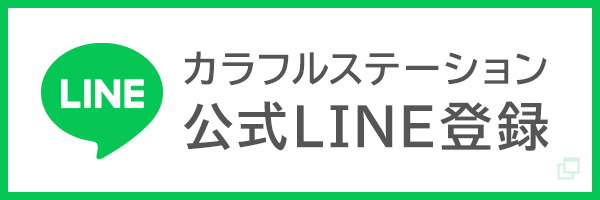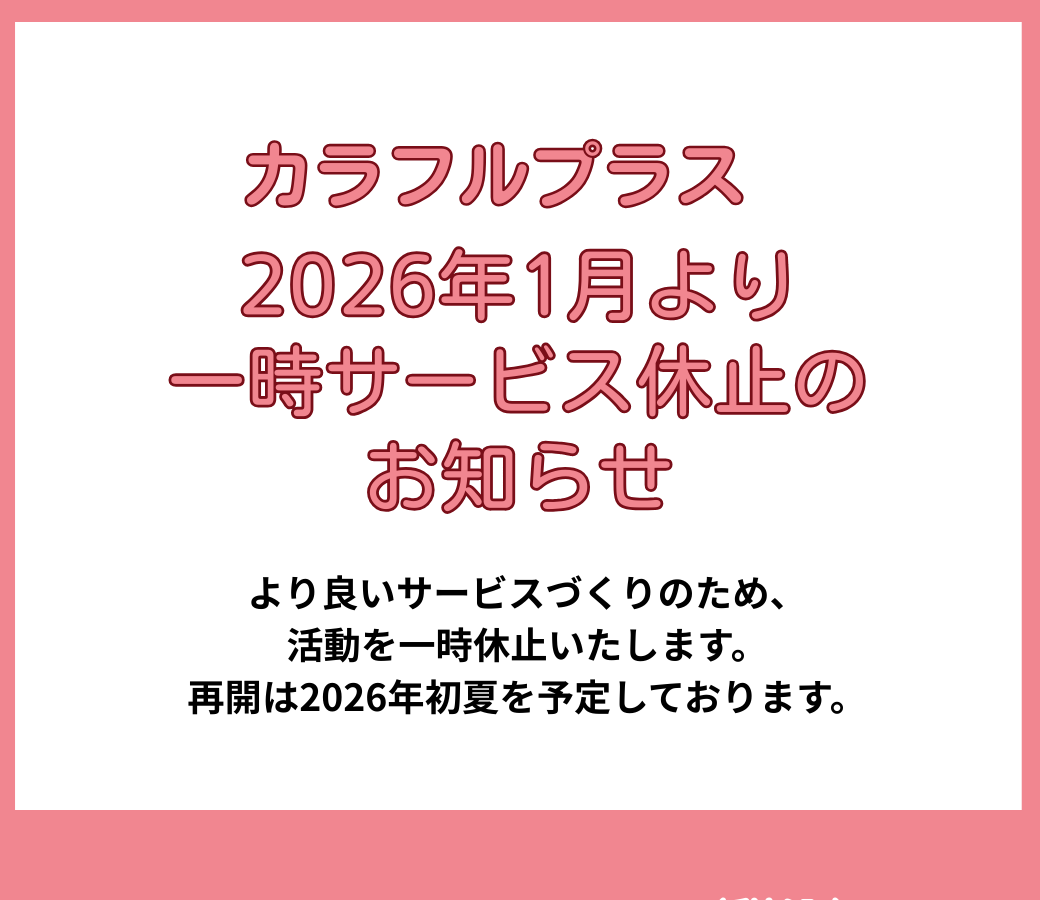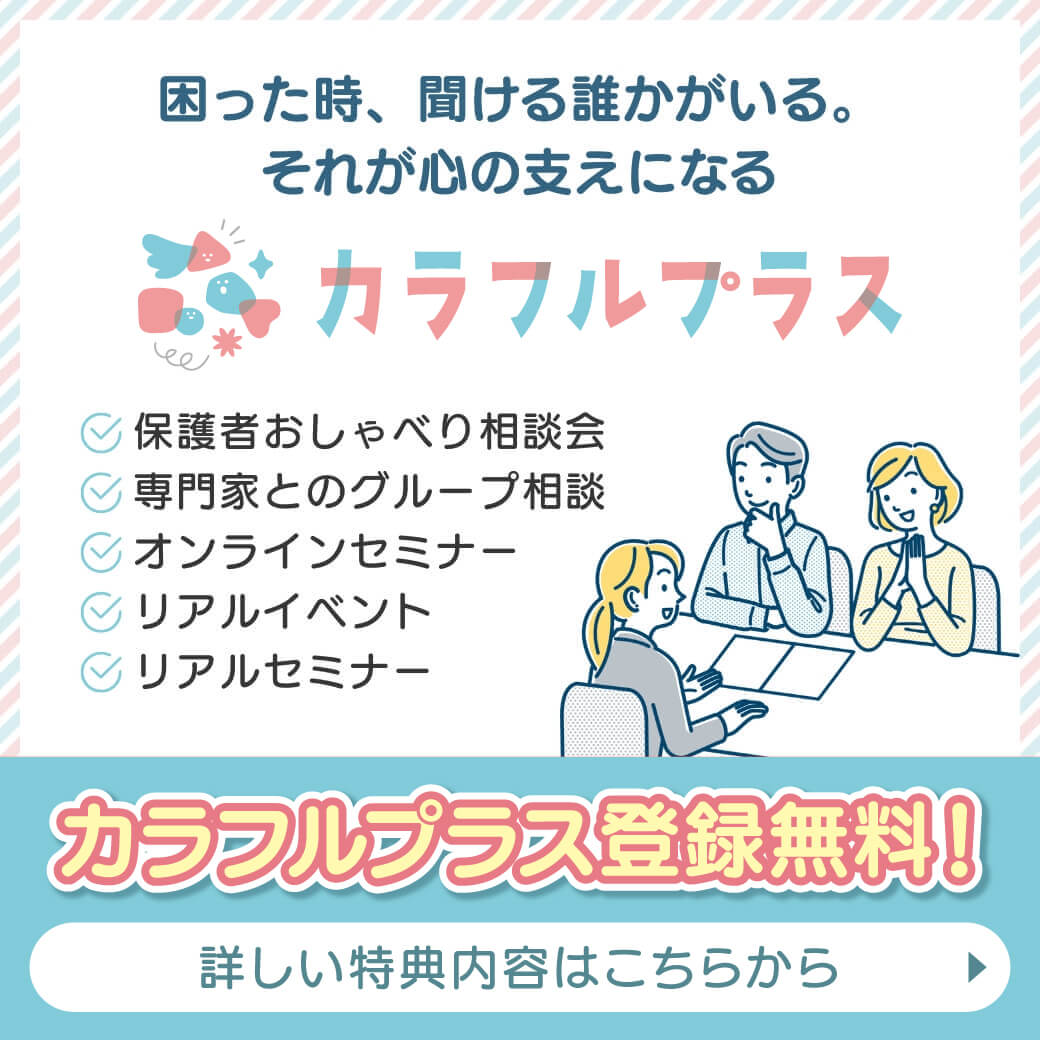「ほら、あいさつは?」「ちゃんとあいさつさせてください!」
学校や地域でそんな声を、かけられた経験はありませんか?
大人の前であいさつができないと、「礼儀がない」「家庭のしつけがなっていない」と受け取られてしまうこともあります。
あいさつは「気持ち」だけではなく、認知の力も必要なスキル
でも、実は発達障害のあるお子さんや、その傾向のあるお子さんにとって、あいさつはとても高度なコミュニケーションスキルです。
たとえば、自閉スペクトラム症(ASD)の特性のあるお子さんの中には、「こんにちは」という言葉が自分に向けられているのかどうか、瞬時に判断するのが難しいことがあります。
耳では音が聞こえていても、それが「自分への呼びかけ」だと気づけない。
その結果、返事ができず、「無視してる」「やる気がない」と誤解されてしまうのです。
これは無関心でもなく、反抗でもなく、「気づけない」ことから起こる反応です。
「相手の意図を読み取る」「声の主を認識する」「自分の反応を選ぶ」このように、複雑な認知と社会的スキルの連携によってあいさつは成立します。
あいさつが難しいのは、決して気持ちの問題だけではないのです。
「伝える」工夫で子どもの反応は変わる
では、どうしたら、子どもにあいさつが届くのでしょうか。
まずは、大人からの声かけを分かりやすくすること。
たとえば、名前を添えて声をかけるだけで、状況は大きく変わります。
「こんにちは」ではなく、「鈴木くん、こんにちは」と伝えることで「自分に向けられた言葉なんだ」と認識しやすくなります。
そしてあいさつの返し方も、ひとつに限定しないことが大切です。
目が合わなくても、返事が小さくても、会釈だけでもOK。
むしろ、その子なりの応答に気づき、受け止めていくことが安心と自信の積み重ねになります。
あいさつは人とつながる はじめの一歩
そして、もうひとつ大切なのが、大人自身があいさつのお手本になることです。
私自身、放課後等デイサービスなどの療育現場で、残念に感じたのは、大人同士のあいさつが交わされていない場面でした。
子どもたちは、大人の言葉や行動からも多くを学びます。
大人が自然にあいさつする姿が、子どもにとって一番のモデルになります。また、家庭や支援の場では、あいさつを練習するのではなく、やりとりとして経験できる環境作りが重要です。
「無理にさせる」のではなく、「あいさつって心地いいな」「返せるとうれしいな」という経験が、社会性の土台を育てていきます。
あいさつは、単なるマナーではなく、人とつながる第一歩。
だからこそ、あいさつができる子に育てる前に、あいさつが伝わる関係を大人が築くことが何より大切なのです。
「どうしたら伝わるか」「どうしたら安心して返せるか」-その視点に立つことが、子どもを尊重する支援のはじまりです。