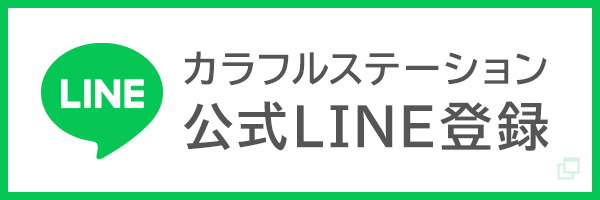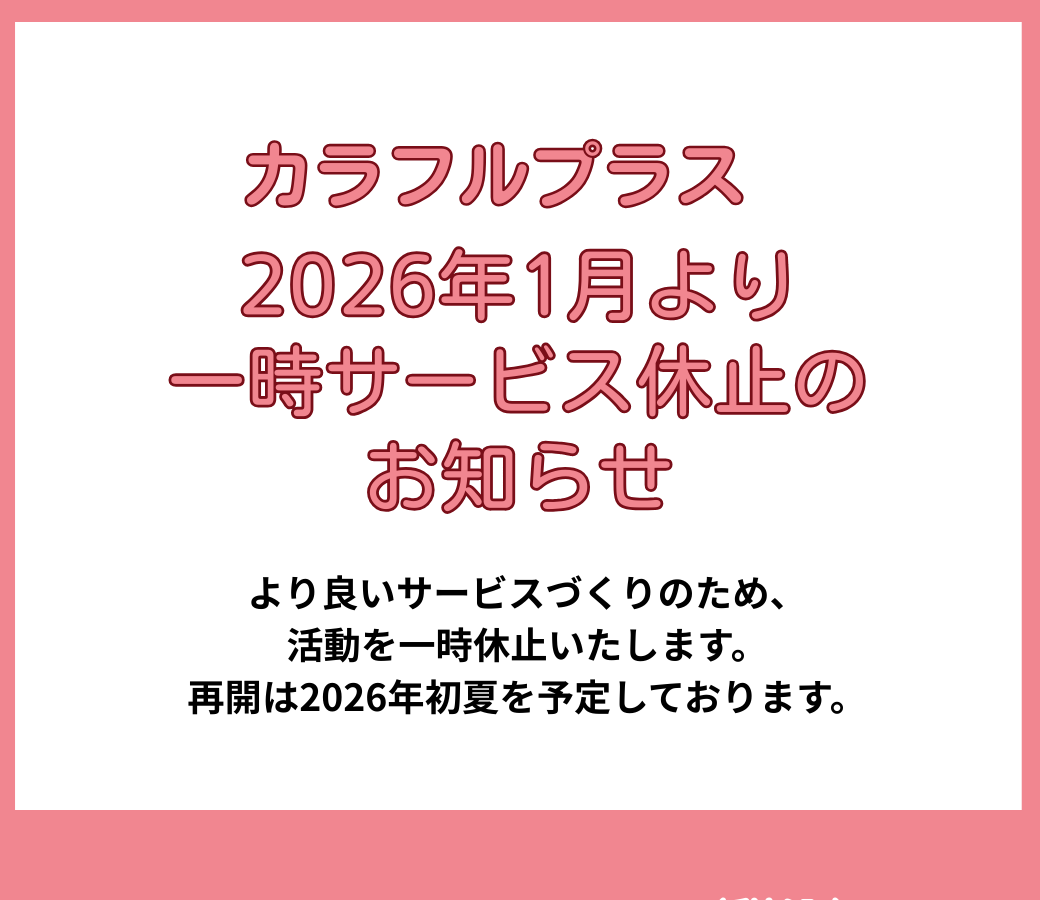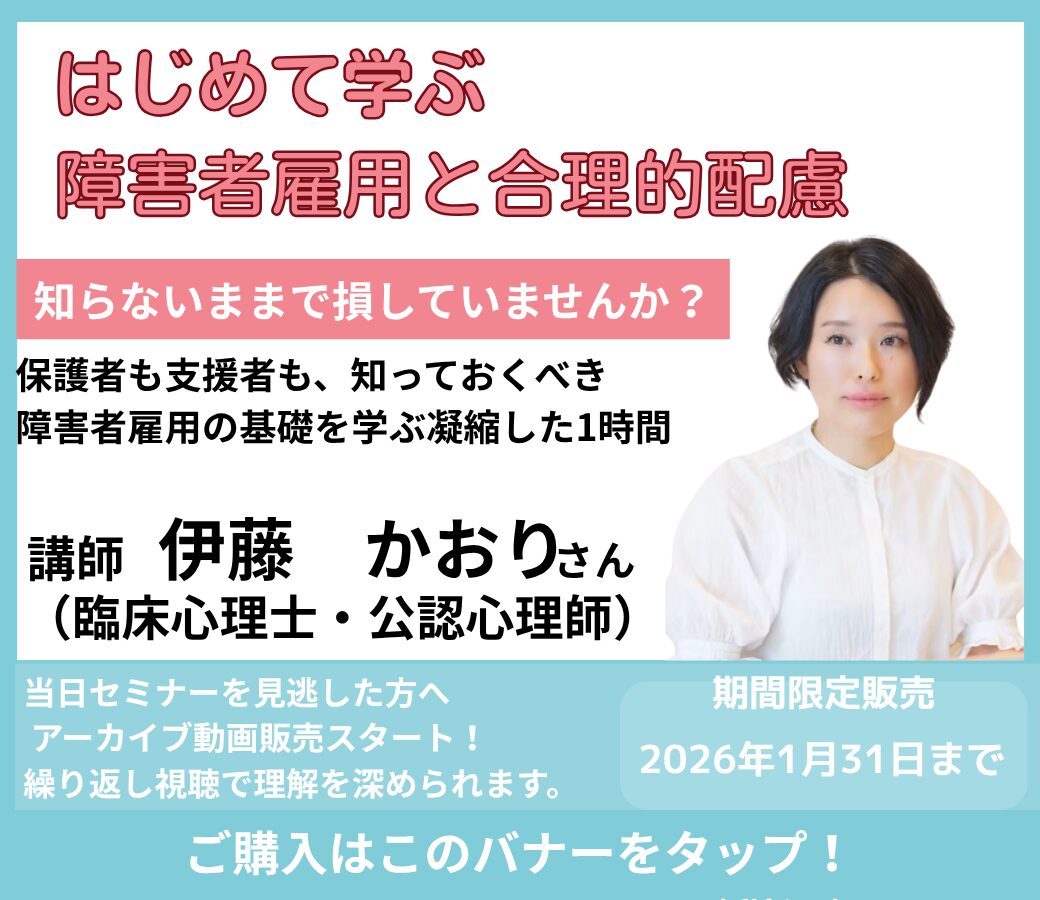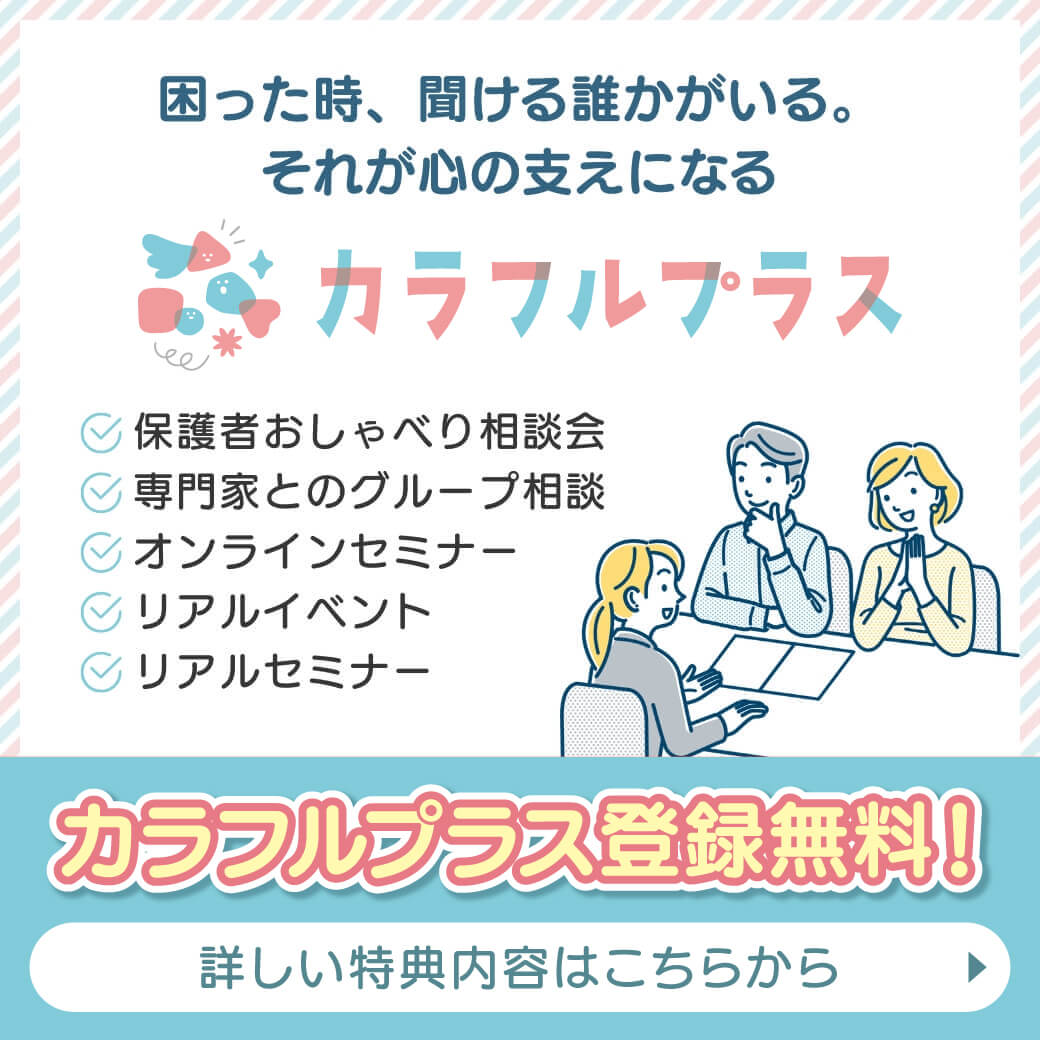「発達凸凹」という言葉を聞いたことはありますか?
子どもの中には、得意なことは人一倍できるのに、苦手なことになると極端に難しさを感じる子がいます。これは「努力不足」や「性格の問題」ではなく、脳の特性による場合があります。
発達障害の研究者である杉山登志郎先生は、こうした「得意と苦手の差」を 「発達凸凹」 とよび、診断に当てはまるかどうかに関わらず、誰にでもある自然な姿だと伝えています。
杉山先生は「発達障害という枠組みだけでは捉えきれない広い層が存在する」と述べ、子どもの発達の違いをもっと大きな視点で見ていくことの大切さを強調しています。
つまり、「発達凸凹」とは子どもがもつ“その子らしさ”の一部なのです。
大人がその視点をもてると、「できない部分」だけでなく「できる部分」「伸ばせる部分」も見えてきます。
発達凸凹の例
発達凸凹がもたらす影響
学校生活の中で「できない部分」として注目されやすく、
子どもが「自分はダメなんだ」と自己肯定感が下がりやすくなります。
一方で、得意なことを認めてもらえれば、自己肯定感が育ち、苦手に取り組む力も湧いてきます。
関わり方のポイント
発達凸凹に向き合うときに大切なのは、苦手を無理に平均に近づけることではなく、得意を伸ばし、苦手を補う工夫をすることです。
小さな工夫で安心できる学びに
・ICTを使った学習支援
・感覚に配慮した環境づくり
・課題を短時間で区切る工夫
などを通じて、安心して学べる場を整えることです。家庭と学校が連携し、子どもの特性を理解して支援することが、劣等感を抱く機会を減らし、「自分はこのままでもいい」と思える力につながります。
まとめ
発達凸凹は、時に「生きづらさ」として現れることがありますが、同時に「可能性の種」でもあります。
子どもの得意を見つけ、周囲が理解し支えていくことで、強みを活かして未来を切り拓く力へと変えていけます。
「できないこと」ではなく「できること」に目を向ける。
そうした関わりが、子どもたちの自己肯定感を育み、安心して成長していける大きな支えになるでしょう。