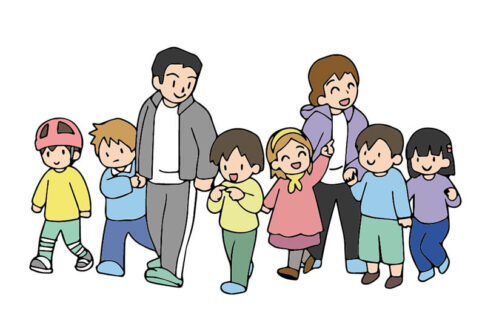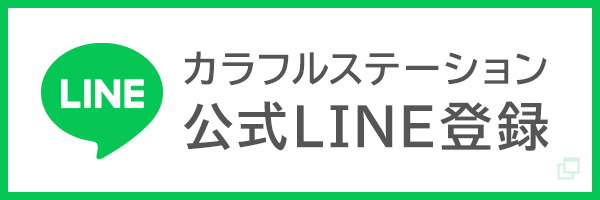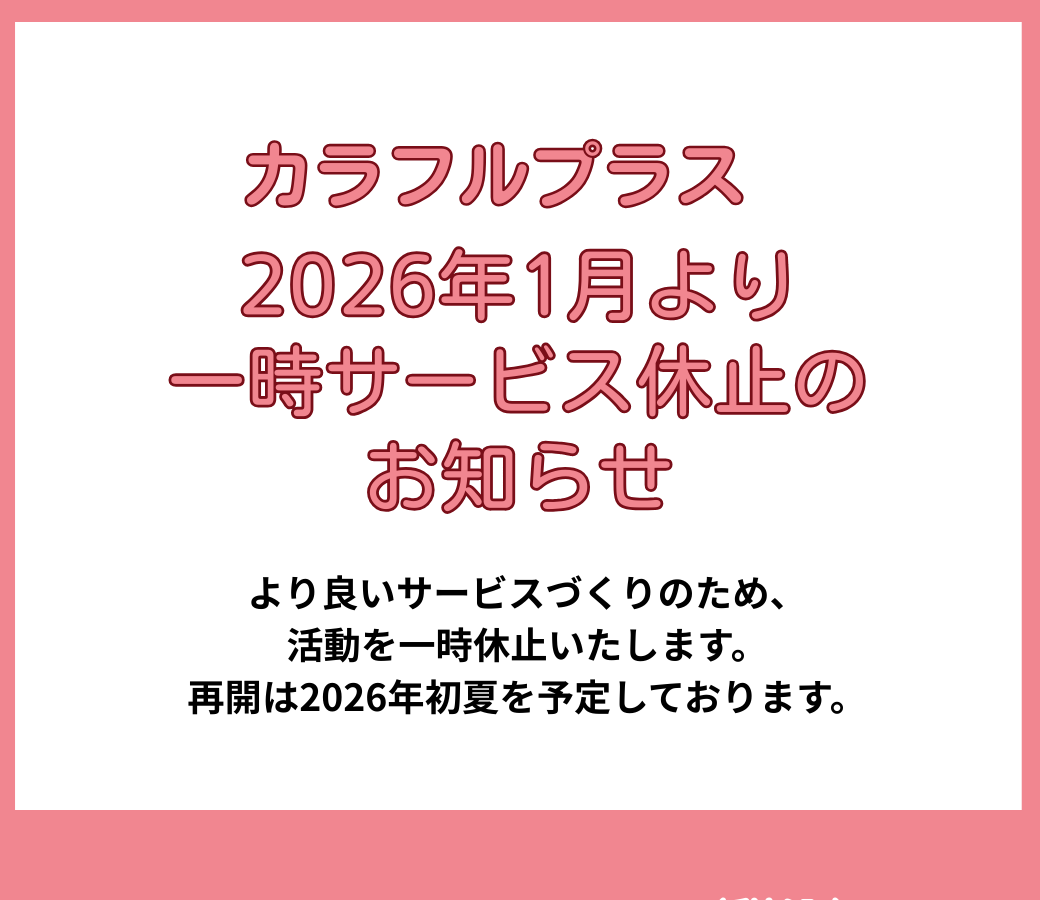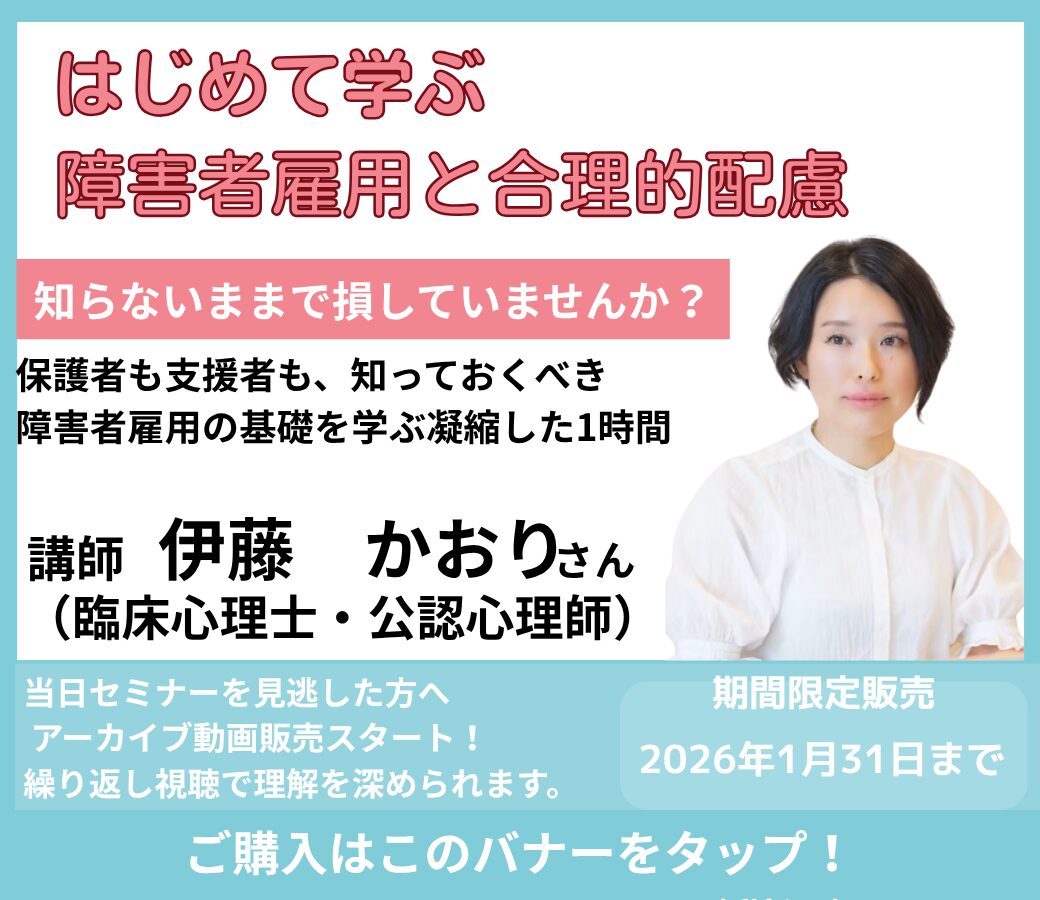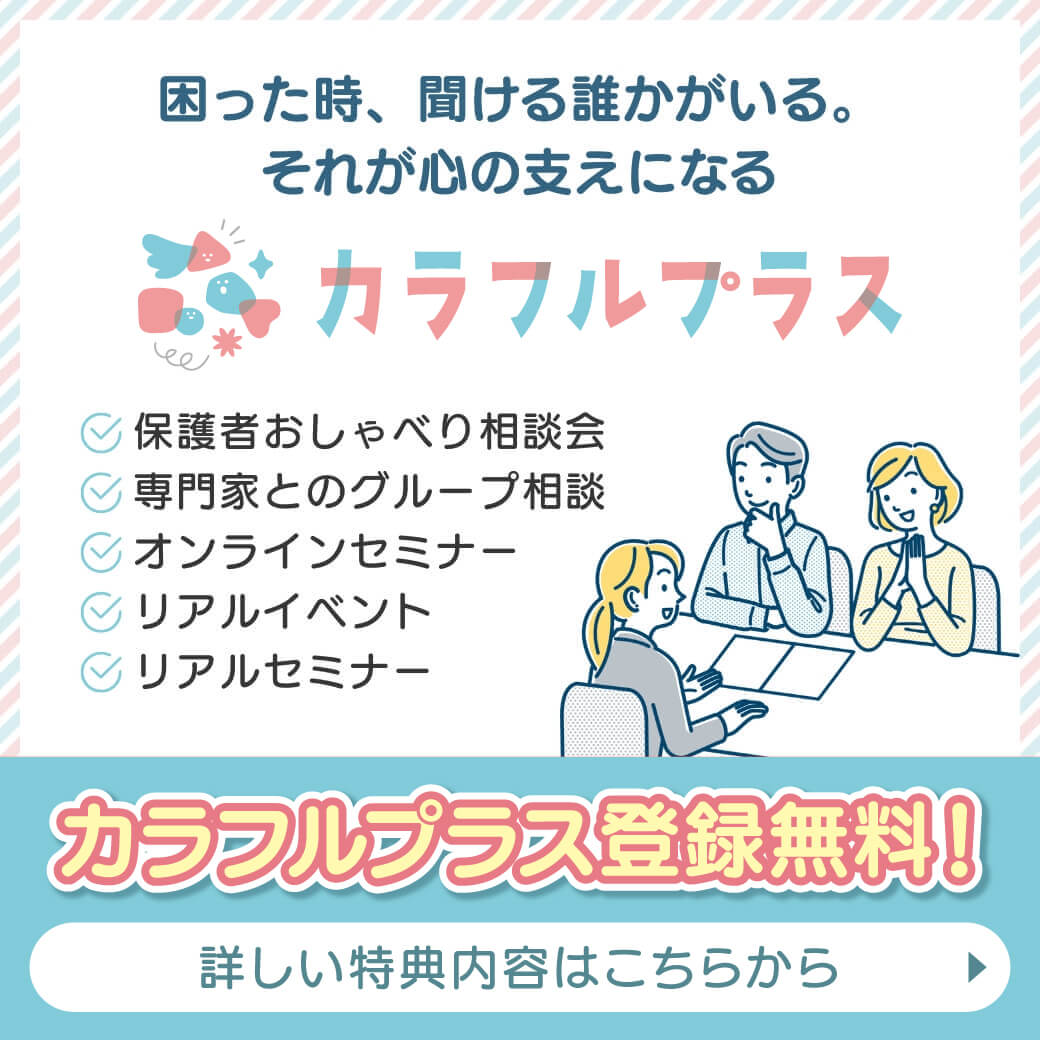「急に泣き出したり、取り乱してしまったり…」
そんなお子さんの姿に、どう声をかけていいか悩んでしまうこと、ありますよね。
今回は、そんな“パニック”の背景や、関わり方のヒントについて、一緒に考えてみたいと思います。
パニックとは?なんで起きるの?
パニックとは、本人にとって不快な刺激や恐怖・不安を感じる出来事がきっかけで、いきなり泣き出したり、耳をふさいでしゃがみこんだり、怒ったように大声を出したりと、感情や行動のコントロールが難しくなる状態のこと。
決して「困らせよう」としているわけではありません。
たとえば、
こうしたことが、その子にとってとてもつらく、耐えきれずパニックに繋がることがあります。
「困った行動」ではなく「困っているサイン」
「泣き叫ぶ」「暴れる」「床に寝転がる」
そんな行動に対して周りの大人が戸惑うのは当然です。
でも、こうした姿は「困らせよう」として出ているわけではなく、
行動として現れたSOS。
だからこそ大切なのは、「どう止めるか」だけではなく、
「なにがその子にとってつらかったのか?」を知ろうとする姿勢です。
ここを理解することが、その子の気持ちを受け止めるきっかけになり、今後の対応のヒントにもなります。
パニックを減らすための工夫
パニックを減らすためにできることはたくさんあります。
こうした工夫が、少しずつ「安心」の土台になっていきます。
実際のエピソードから
聴覚が過敏なお子さんで、苦手な音がパニックのきっかけになることがありました。
ある日、豪雨の中で雷が鳴りそうな時、その子の不安を少しでも軽くするために、事前に伝えてみることにしました。
「〇〇君、暗くなってきたからこのあとゴロゴロって雷が鳴るかもしれないよ。怖かったら、先生のお洋服をぎゅっと握ってね」
少し不安そうな表情はありましたが、実際に雷が鳴ったときはパニックにならず、僕の衣服に触れることで落ち着いていました。
このように、事前に伝えたり、不快を感じたときの安心できる行動の選択肢があることも子どもの安心につながるのです。
まとめ
子どもがパニックを起こしたとき、大人に求められるのは、観察と思いやりのまなざしです。
「どうしてパニックになったんだろう?」
「何が怖かったんだろう?」
「もしかして、この刺激がつらかったのかも?」
そう問い直すことが、次の関わりにつながります。
「この子を分かりたい」という気持ちが、もっとも大切な支援のはじまり。
このコラムが悩んでいる誰かの心を、少しでも軽くするきっかけになればうれしいです。