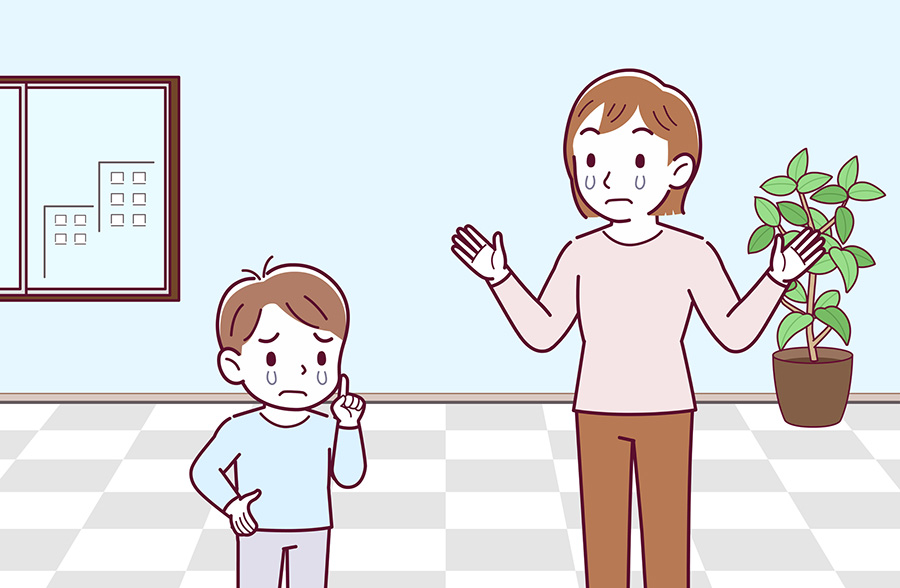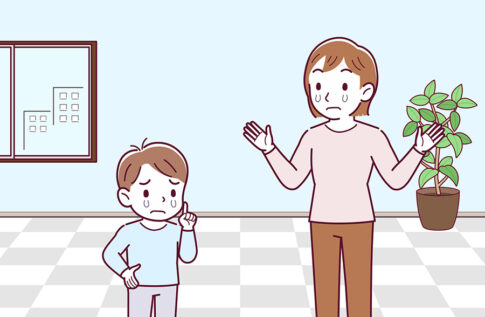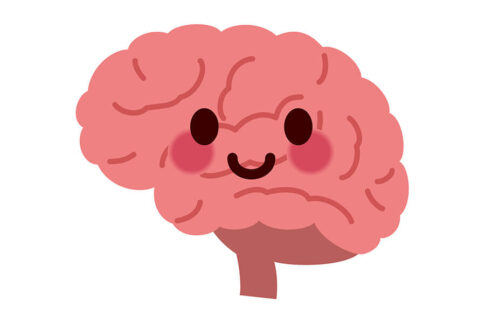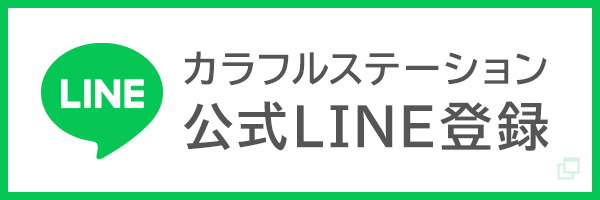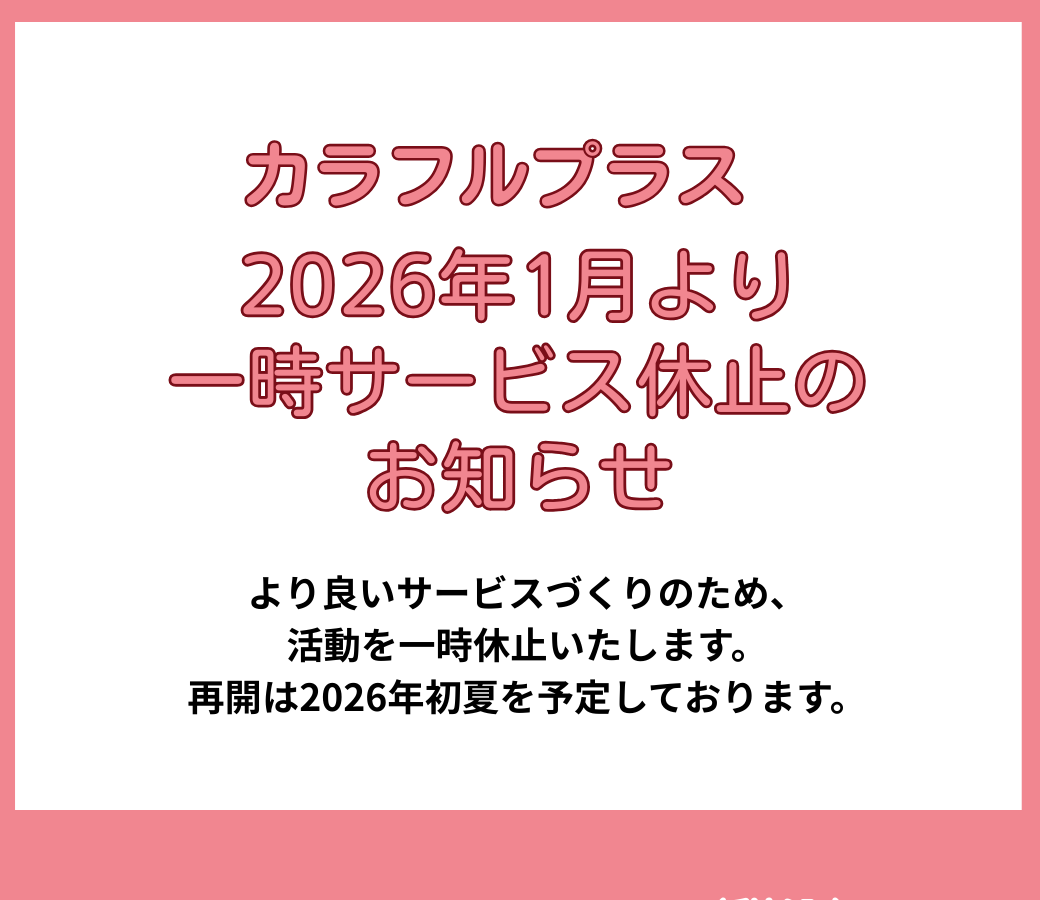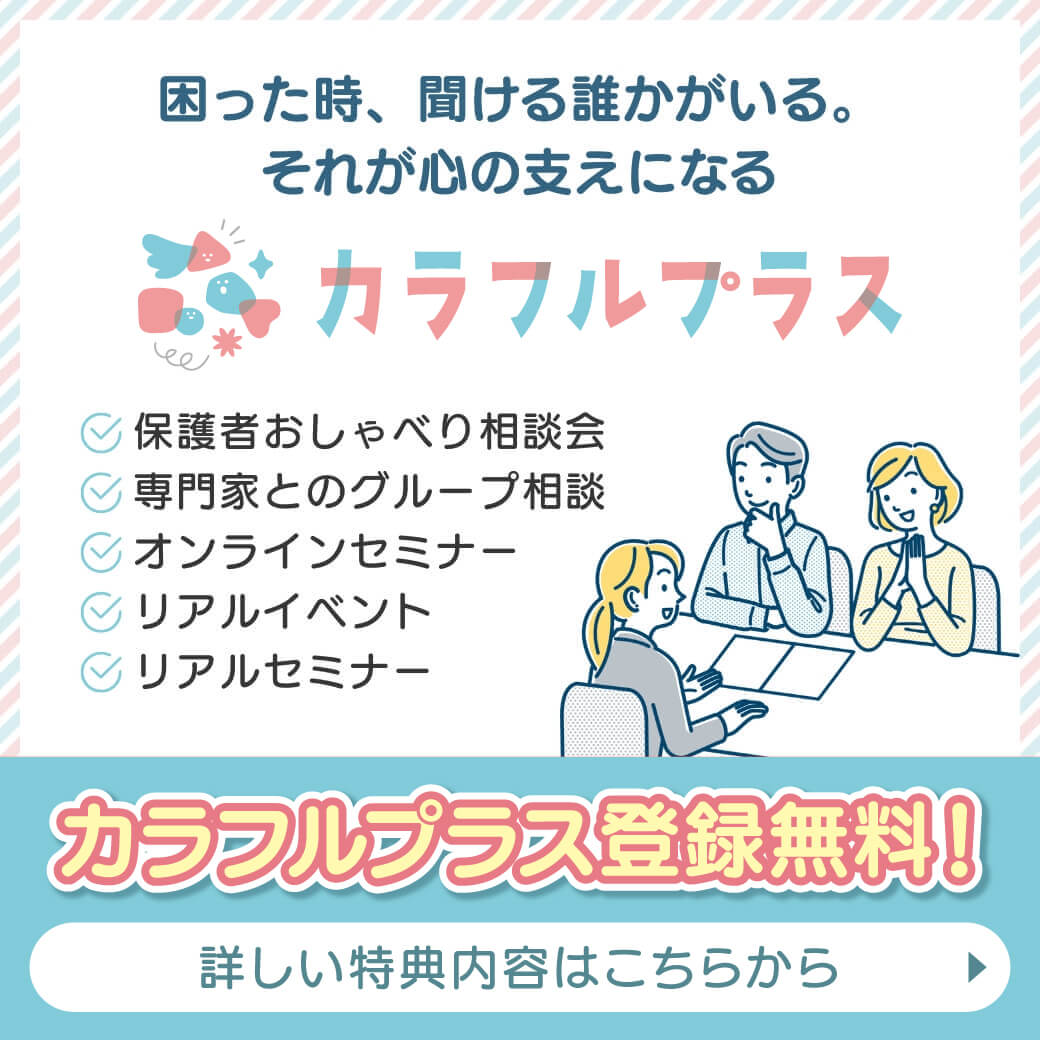「また怒ってしまった…」と自己嫌悪になるとき
発達障害やグレーゾーンのお子さんを育てていると、一般的な子育ての本に書かれている方法が通用しないことがあります。
「分かっているのにイライラしてしまう」
「優しくしたいのに怒鳴ってしまった」
そんな自己嫌悪を抱くママやパパは少なくありません。
でも、それは親の頑張り不足ではなく、子どもの特性ゆえに起きやすいことなのです。
イライラは「心のSOSサイン」
認知行動療法(CBT)という心理療法では、心の反応は次のようにつながっていると考えます。
たとえば
出来事:何度も癇癪を起こす
↓
受け止め方:「私の育て方が悪いのかも…」と考えてしまう
↓
感じ方:気持ちがいっぱいいっぱいになる
↓
行動:怒鳴ったり、「もう知らない」と突き放して関わるのをやめてしまう
このように、CBTでは、出来事そのものではなく「どう受け止めるか」で感情や行動が変わっていくと考えます。
つまり、子どもの癇癪を、「親がダメだから」と受け止めてしまうと、どうしてもイライラが大きくなってしまうものです。
でも実は、そのイライラは「心が疲れているよ」と知らせてくれるSOSサインなのです。
ストレスコーピングという考え方
心のサインに気づいたときに役立つのが『ストレスコーピング(=ストレスへの対処法)』です。
発達障害児の育児は長期戦だからこそ、ママやパパ自身が心を守るための『セルフケアの引き出し』を持っておくことが大切です。
コーピングにはいくつか種類があります。
大事なのは、全部を完璧にやることではなく、自分に合う方法をひとつ見つけることです。
そして、少しずつ引き出しを増やしていければ、より安心につながります。
たとえば「今日はノートに一言だけ気持ちを書いてみる」だけでも、頭の中の“ぐるぐる”が整理されるひともいれば、「書くのは苦手だけど、同じ境遇の人と話すと楽になる」という人もいます。
完璧よりも「一緒に練習」でいい
発達特性のある子育ては、うまくいかない日があって当たり前です。
大切なのは「今日できたかどうか」ではなく、「今日はこんな方法を試してみよう」と思えること。
まずは自分に合う方法をひとつ見つけることから始めましょう。
そして余裕が出てきたら、少しずつレパートリーを広げれば十分です。
ママやパパが安心を取り戻すことが、子どもの安心の土台にもなります。
親が落ち着いていられると、自然と子どもにも伝わっていきます。
どうか「私が弱いから」ではなく、「セルフケアの練習中なんだ」と思ってください。
その一歩が、親子にとって大きな力になります。