障害のある子どもは、特性による困難だけでなく、周囲の理解不足や環境とのミスマッチによって、「二次障害」を併発しやすい傾向があります。
これは本人の努力不足によるものではなく、経験や環境によって、引き起こされるものです。
二次障害の例
学校や友人関係になじめず、頭痛・腹痛・不眠などの身体症状が現れることがあります。
集団での活動が基本となる場面では、周囲に合わせることが難しい子どもは負担を感じやすくなります。
特に刺激に敏感な子どもにとっては、集団生活自体がストレスになることもあります。
叱責や失敗体験が続くと自信を失い、攻撃的・反抗的な態度が増えることがあります。
「分かってもらえない」という気持ちのあらわれであることもあります。
二次障害への対処法
気になる様子が見られたら、スクールカウンセラー、精神科、発達障害者支援センターなど、専門家および専門機関への相談を検討しましょう。
必要に応じて、薬物療法やカウンセリング、SST(ソーシャルスキルトレーニング)などの支援を受けられる場合もあります。
静かに過ごせるスペースを作る、スケジュールを視覚的に提示するなど、安心して過ごせる環境づくりが重要です。
環境を少し整えるだけで、負担が大きく軽減することもあります。
子どもが自分の特性を理解し、それを受け入れることができると、二次障害の予防や軽減につながります。
たとえば、「自分は忘れ物をしやすいから、必要なものは前日に玄関に置いておく」といった捉え方や工夫ができると、自己肯定感の回復にもつながります。
大人が寄り添い、そうした取り組みを支えていくことによって子どもに安心感を与え、成長を支えます。
まとめ
二次障害は、早めの気づきと適切な支援によって、症状が改善することも十分期待できます。
子どもたちが自分らしく安心して成長していけるよう、温かく見守り支えていきたいですね。
(参考文献)
・滝川一廣(2017)子どものための精神医学 医学書院
・杉山登志郎(2007)発達障がいの子どもたち 講談社現代新書
・田中康雄(2008)わかってほしい!気になる子 学習研究社
・浜内彩乃(2024)流れと対応がチャートでわかる!子どもと大人の福祉制度の歩き方 ソシム株式会社





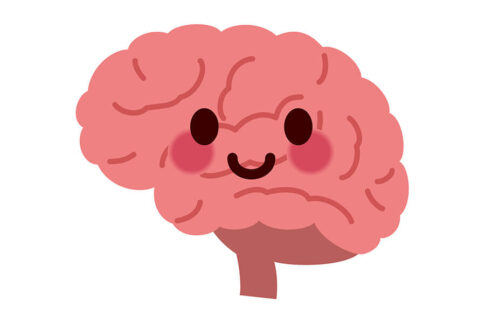
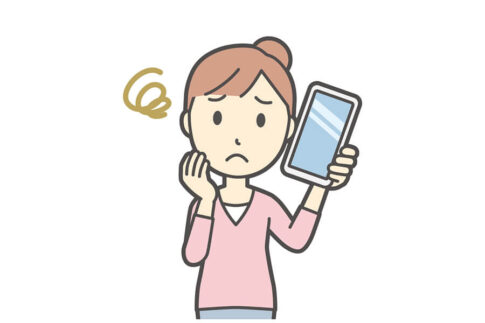



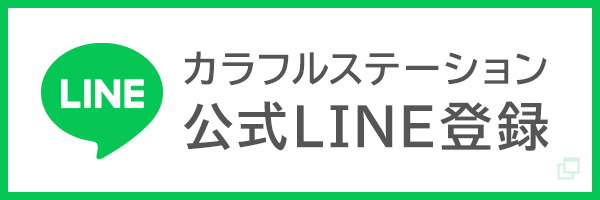
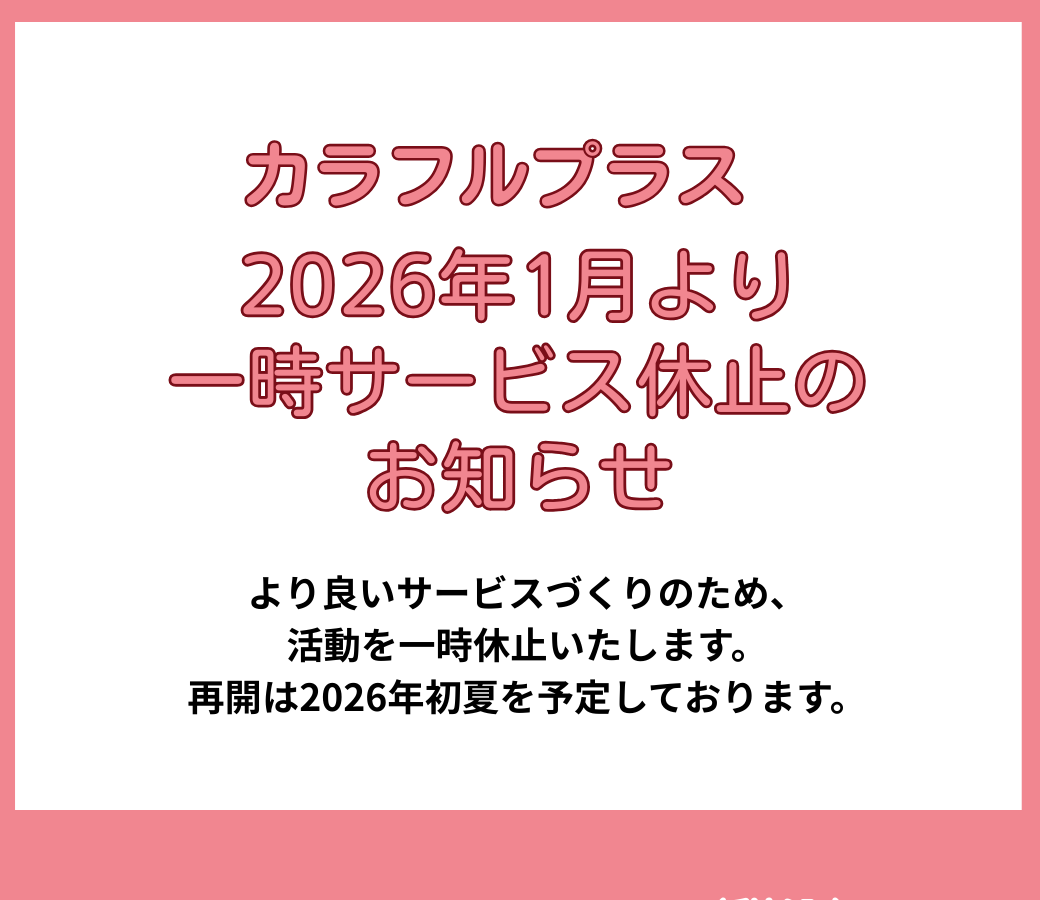





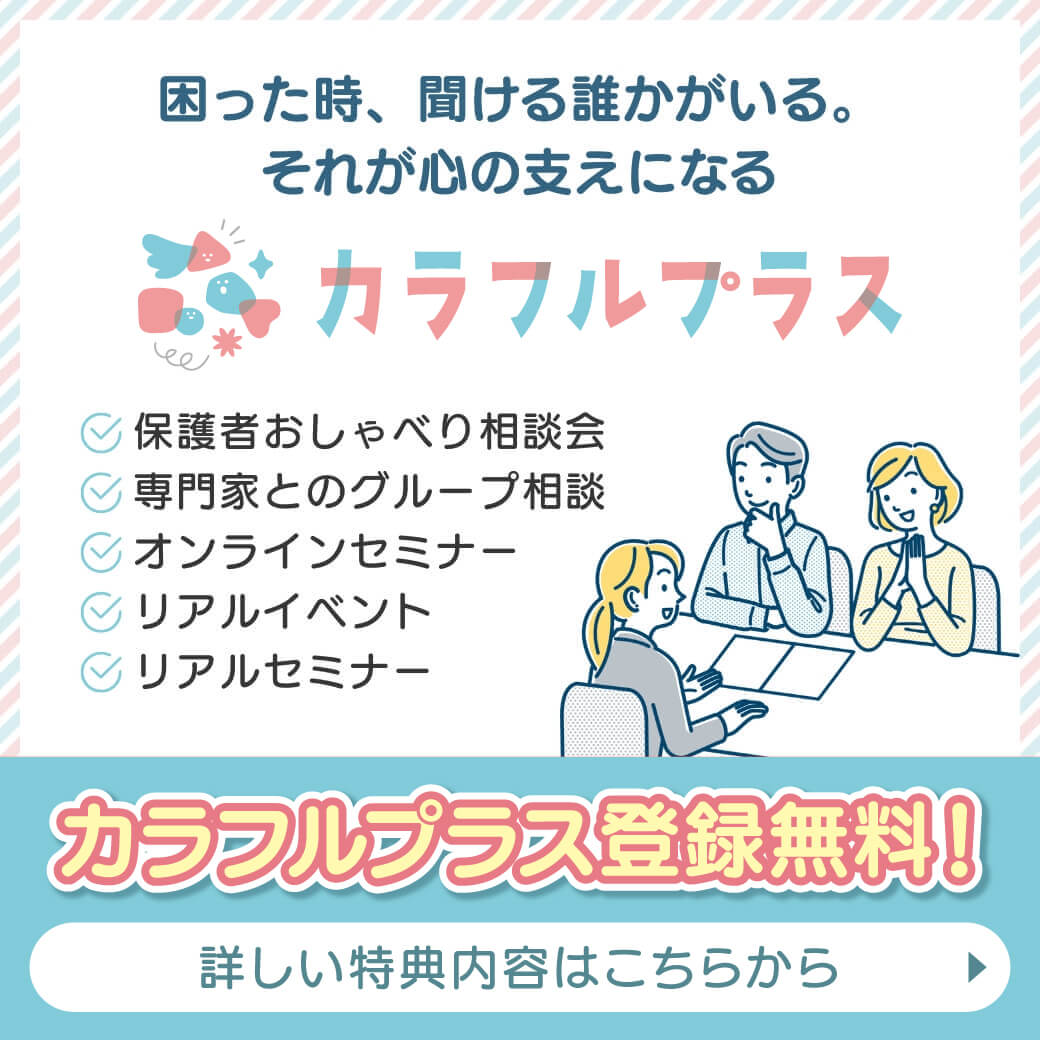
ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如多動症)のある子どもは、失敗体験などから自己否定を繰り返し、「自分はダメだ」と考えやすく、不安や抑うつを抱えやすい傾向があります。