お子さんの発達に心配があると、「大人になったとき、この子は働けるのだろうか」と不安になることはありませんか?
今回は「障害者雇用」と「合理的配慮」に注目し、現状と課題を見ていきたいと思います。
障害者雇用とは、一般企業にて障がいのある人が障がい者枠で働くことです。
周囲に支援者がいない環境での仕事は本人にとって不安が大きく、受け入れる側の従業員も戸惑うことがあります。
そのため、障がいのある方だけでなく企業内の理解を得ながら、丁寧な準備と継続的なフォローが欠かせません。
ここで知っておきたいのが法定雇用率です。
これは「従業員のうち一定の割合を障がいのある人が働けるようにしましょう」と国が定めた基準で、2024年4月から民間企業は2.5%になりました。2026年7月からは2.7%に引き上げられる予定です。
ただし、法定雇用率を達成している企業は46.0%にとどまり、まだ半数以上の企業が障害者雇用に取り組んでいません。
保護者の方にとっては、少し残念なお話かもしれませんが
といった理由で、企業が足踏みしているのが実情です。
一方で、前向きな動きもあります。
2024年4月から、事業主による「合理的配慮の提供」が法律で義務化されました。
これまでは努力義務でしたが
今は「しなければならない」ルールです。
実際に企業でも成果が出ています。
IT企業では発達障がいのある社員が「細かい違いに気づく力」を活かしてシステムテストで活躍しています。大手カフェでは聴覚障がいのあるスタッフがタブレットを使って接客し、お客様からも好評です。
また、大企業だけでなく、地域の中小企業でも障害者雇用に積極的に取り組む例は増えています。
保護者として大切なのは、今から
「得意を伸ばすこと」「苦手を工夫で補うこと」を意識して見守ること。
そして、社会全体も同じ方向に動いていると知ること。
それが、わが子の未来を少し明るく見通すヒントになるはずです。




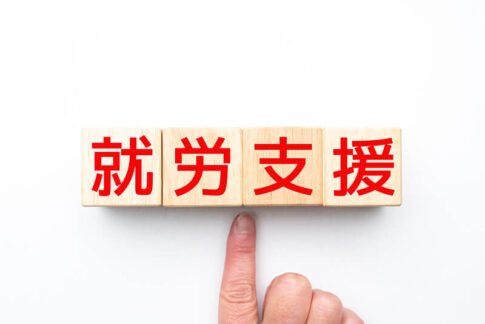






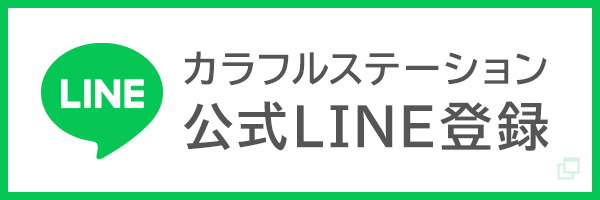
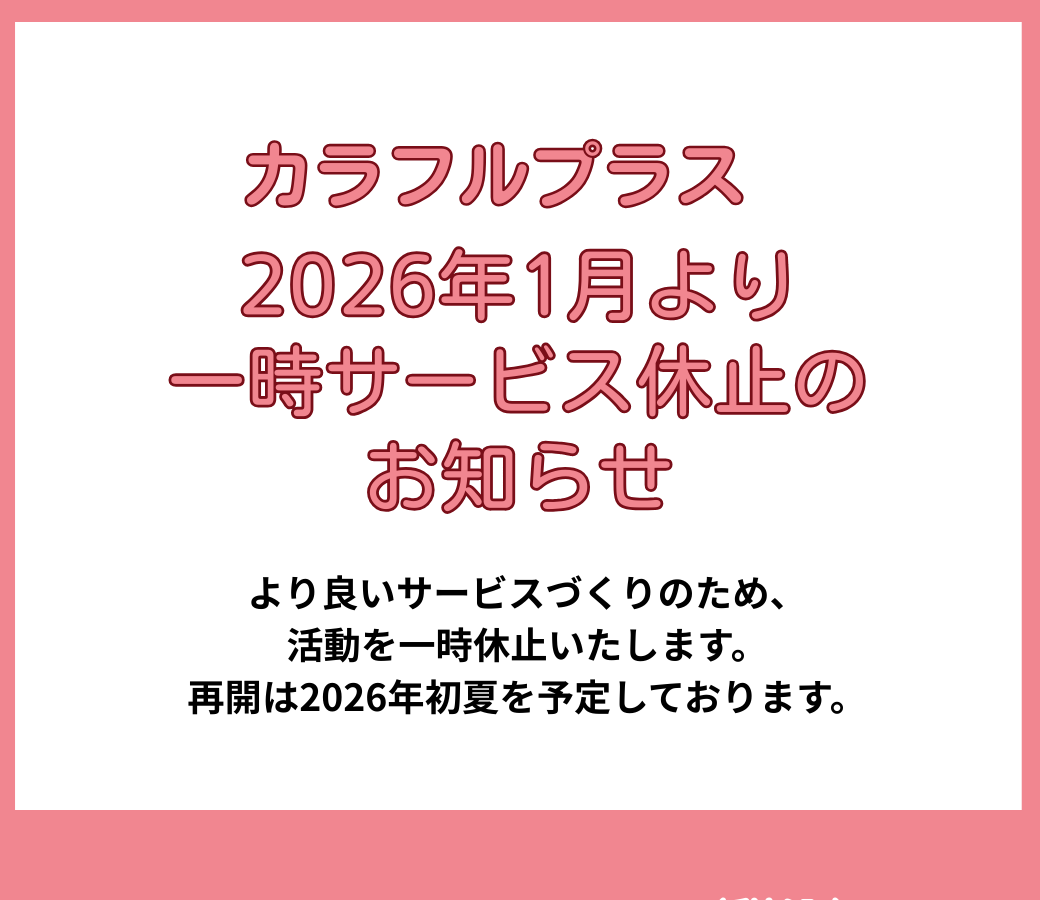





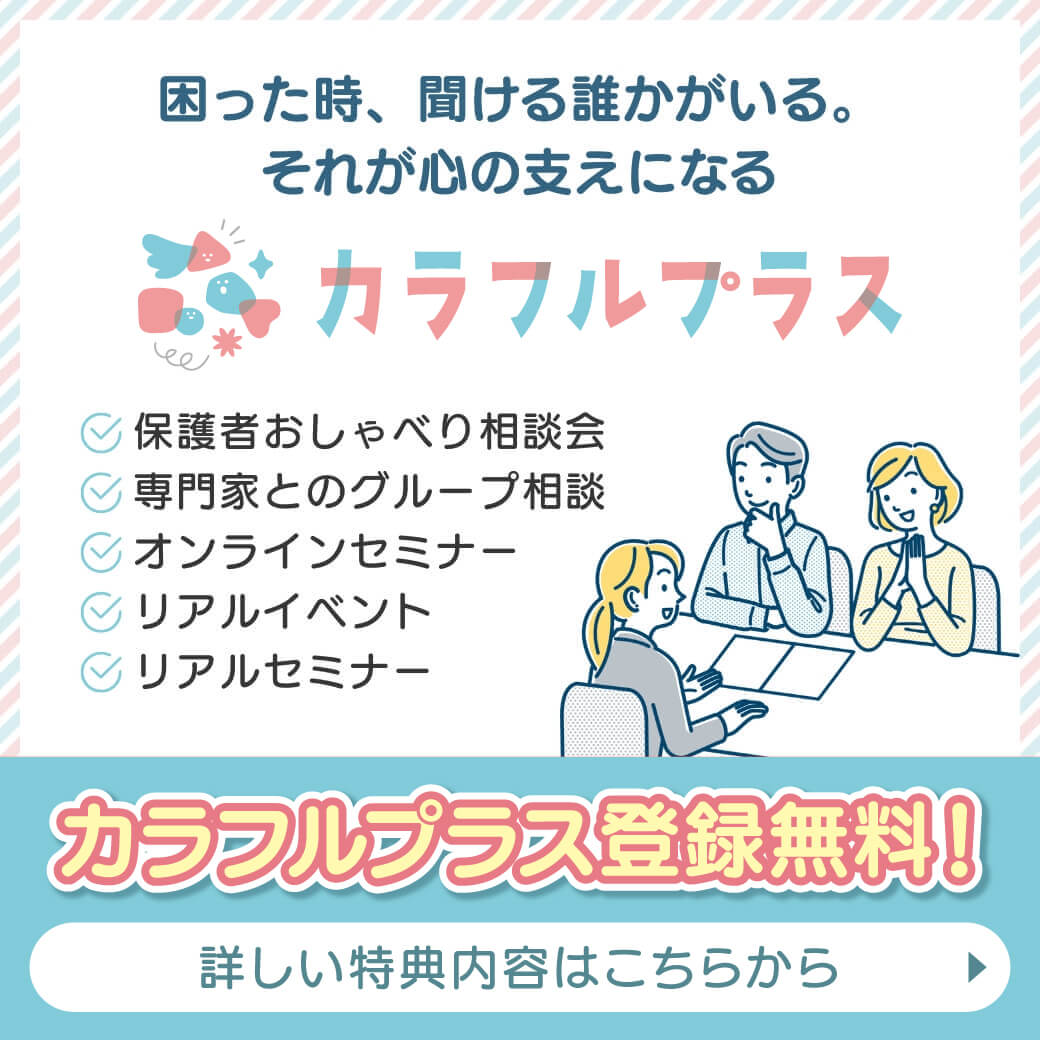
障がいのある人が力を発揮できるように職場環境を整えることです。発達障がいのある人には作業を分けて伝える、聴覚障がいのある人には文字やタブレットでのやりとりを活用する、車いす利用者には段差をなくす。こうした調整が、合理的配慮です。