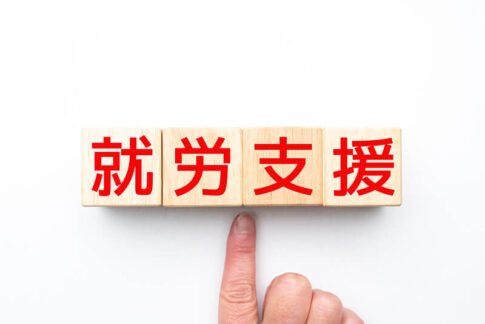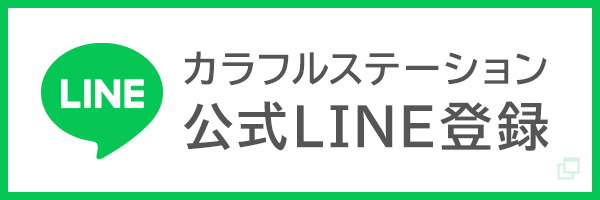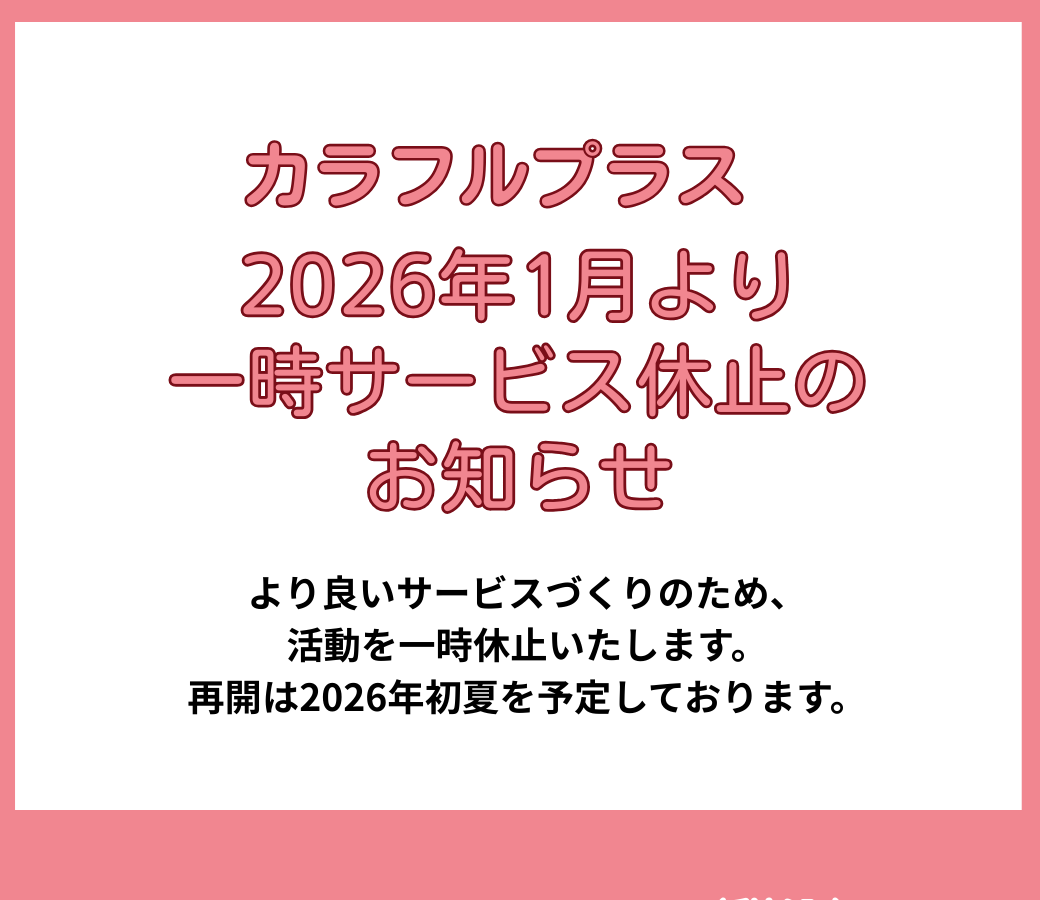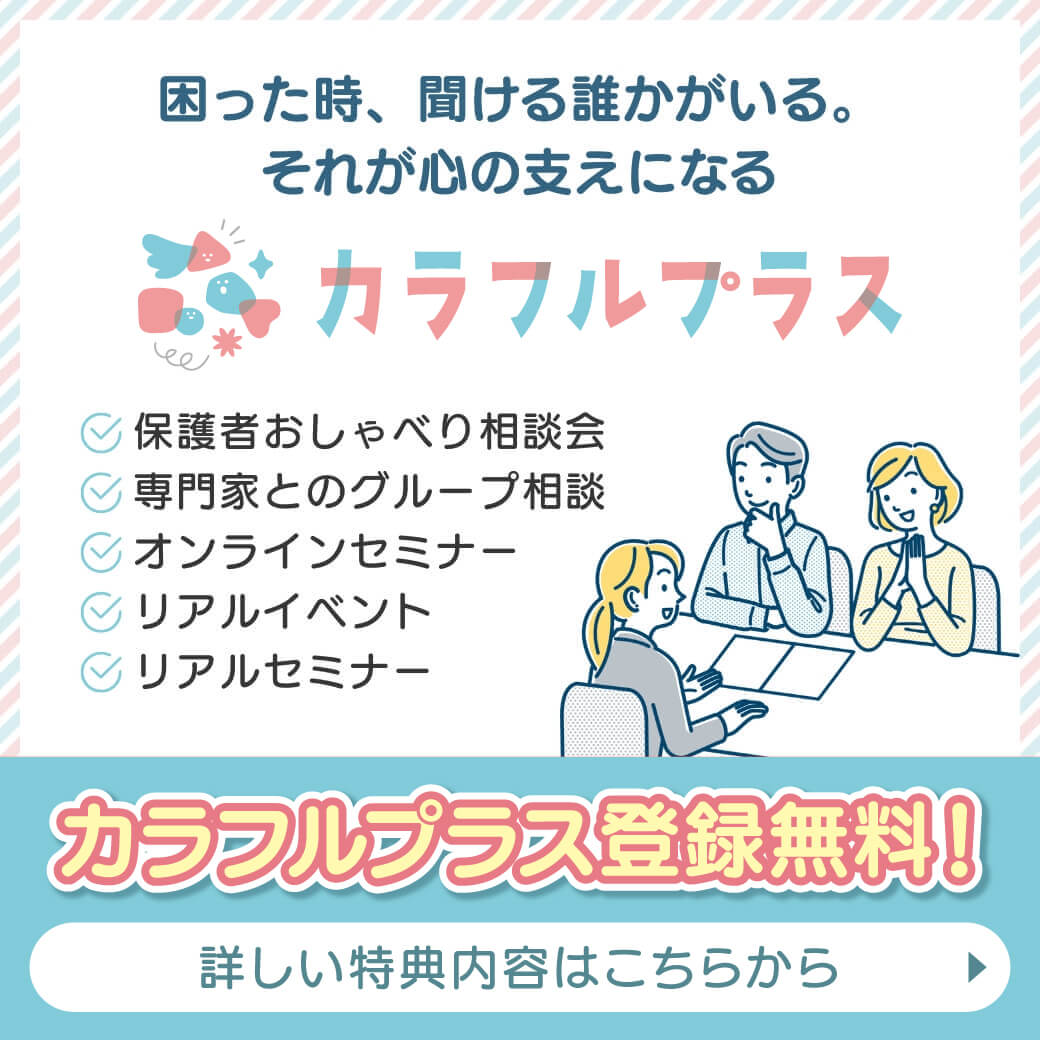お子さんに発達に心配があると告げられた時、ふと、”将来、この子は働けるのだろうか・・・”と不安になったことはありませんか?
「働く」とひと口に言っても、障害のある方の就労には、大きく分けて、次の3つのパターンがあります。
障害のある人の就労 3つのパターン
1つ目は、一般の人と同じ枠で働く「一般就労(クローズ)」です。
障害のことは職場に伝えずに働くスタイルで、サポートは特に受けない働き方です。
2つ目は、障害者雇用枠での就労です。
こちらは障害があることを企業に伝え、配慮を受けながら働く方法で、身体・知的・精神のいずれかの手帳が基本的には必要です。企業には、「障害者雇用率制度」があり、一定の規模の会社であれば、一定数の障害者を雇用する義務があるため、年々この枠での雇用も増えています。
3つ目は、「福祉就労」と呼ばれるものです。
これは、「障害者総合支援法」に基づいて運営されている就労支援事業所(就労継続支援A型・就労継続支援B型)で働くスタイルです。詳しくは【後編】でご紹介します。
障害者雇用枠での就労スタイル
障害者雇用枠には、いろいろな就労スタイルがあります。
特例子会社は、障害者雇用に特化した子会社で、主に障害のある方が集まって働く場です。
この会社で働いている障害者の人数が、親会社やグループ会社の障害者雇用率にカウントされます。
作業内容や職場の環境を、障害特性に合わせて整えやすいのが特徴です。
例えば、親会社から引き受けた仕事を、静かな環境でゆっくり取り組めるように工夫しているケースもあります。
最近話題になることも多いのが、「障害者雇用代行ビジネス」という新しいスタイルです。
これは、障害者雇用率を達成できていない企業等が雇用した障害者が、別の事業者が提供する職場に勤務することで、企業の「雇用率達成」に貢献するというもの。
法律上は問題はありませんが、障害者の「働く意義」や「社会参加」といった本来の目的に照らし合わせると、良いのかどうか議論があるのも事実です。
まとめ
皆さんのお子さんは、今おいくつでしょうか?
福祉制度は3年ごとに見直され、新しい仕組みや働き方も次々と生まれています。今の話が、5年後、10年後も同じとは限りません。
つまり、先輩の体験談が必ずしも我が子に、そのまま当てはまるとは限らないのです。
我が子の成長を見守りながら、就労の情報もアップデートしていけたらいいですね。