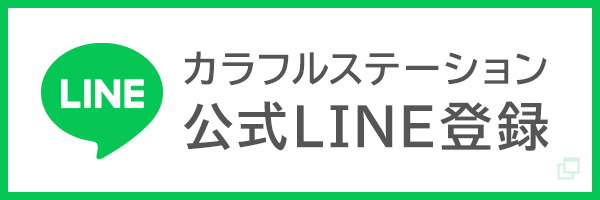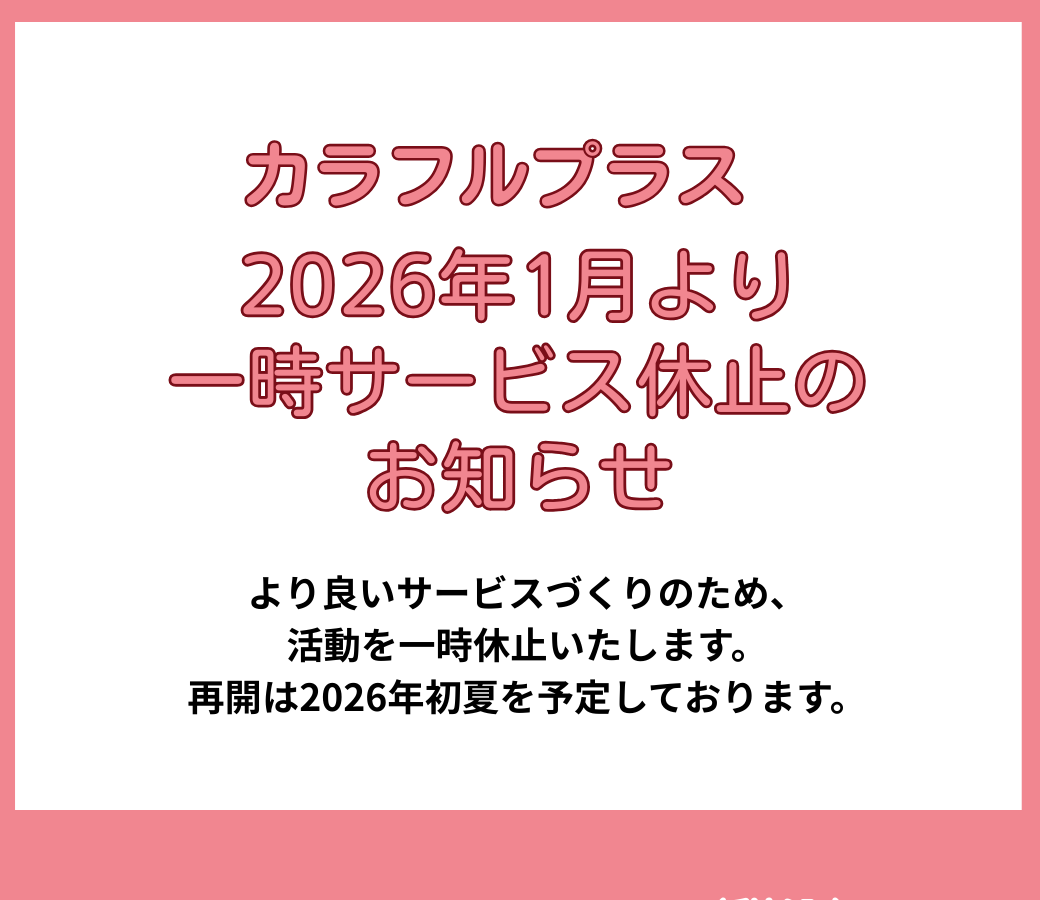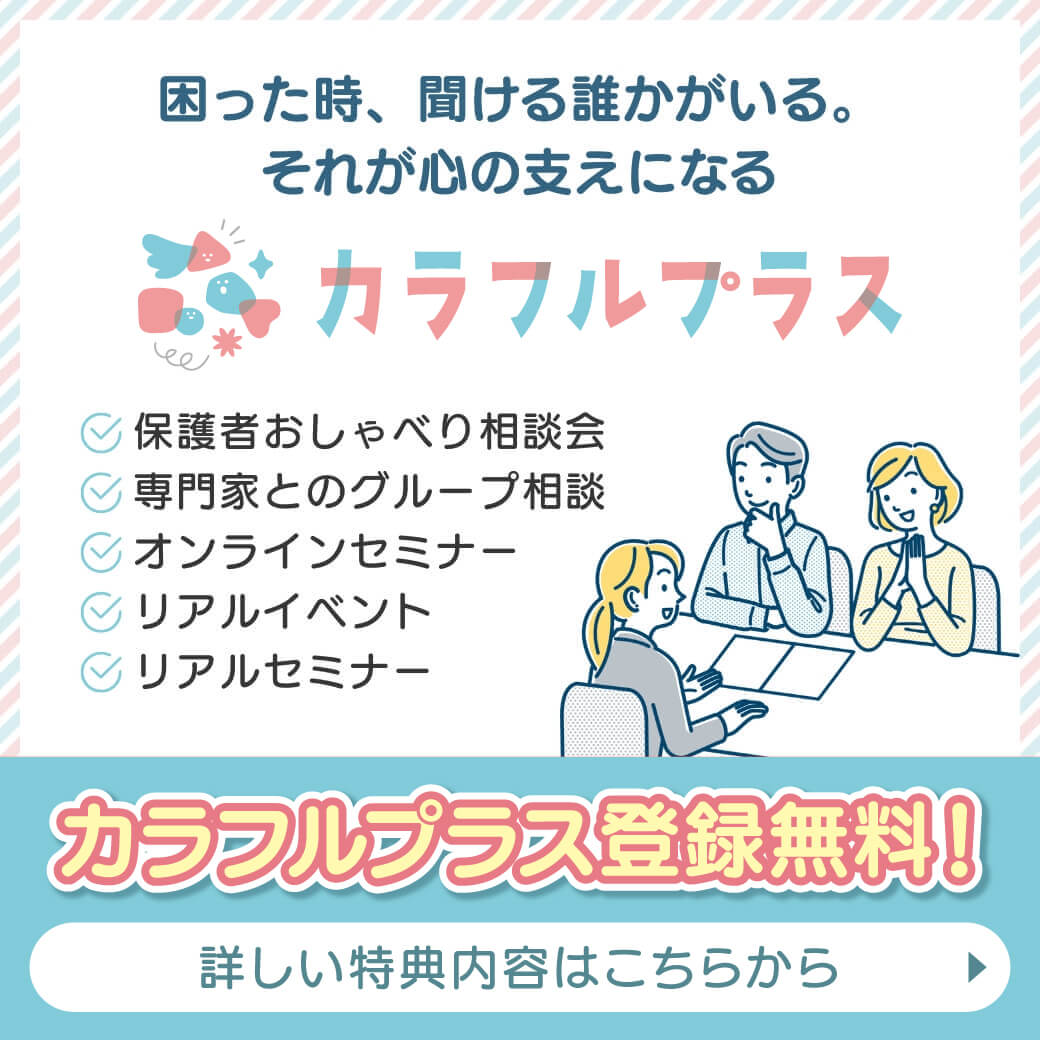そんなふうに、お子さんの食事について悩まれている保護者の方もいらっしゃるかもしれません。
実はこうした偏食の背景には、感覚の特性が関係していることがあります。
感覚には、皮膚にある感覚(触れた感じ、痛み、温度、圧迫を受ける感じ)や五感(味・音・におい・触れた感じ・見た目)に加え、バランスを感じる力(前庭覚)や身体の動きを感じる力(固有覚)など、さまざまな種類や分類があります。
これらの感覚が敏感だったり、逆に感じにくかったりすると、食事の場面で困り感があらわれることがあります。
今回は、感覚の中でも「温度(温覚・冷覚)」「におい(嗅覚)」「触れた感じ(触覚)」に注目し、ちょっとした工夫をいくつかお伝えします。
温度に過敏なお子さんの場合
などの様子が見られることがあります。
熱さや冷たさが、口の中で痛みのように感じられているのかもしれません。
少し冷ましたり、常温に戻してから出すことで、食べやすくなることがあります。
においに敏感なお子さんの場合
など、においに対して敏感に反応することがあります。
不快に感じるにおいは、ただ嫌というだけでなく、気分が悪くなってしまうこともあるため、調理法を工夫したり、においの少ない食材を選ぶのもひとつの方法です。
口の中の触れた感じに敏感なお子さんの場合
など、口の中に入れた時の触り心地で嫌がることがあります。
これは口の中が敏感で、チクチク感じたり気持ち悪く感じたりするためです。
触感を変えたり、苦手な部分を取り除いてあげることで、食べやすくなることがあります。
今回のまとめ
「食べない=わがまま」と決めつけず、「もしかして感覚に理由があるのかも」と見つめ直してみると、少しずつ食事の時間が楽になっていくかもしれません。
後編では、見た目や身体の感覚に注目し、工夫についてお伝えします。