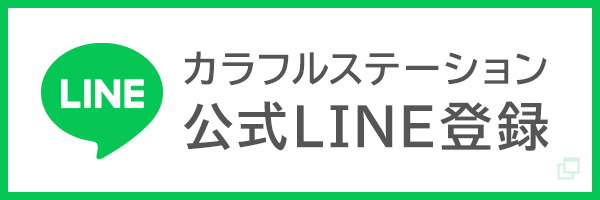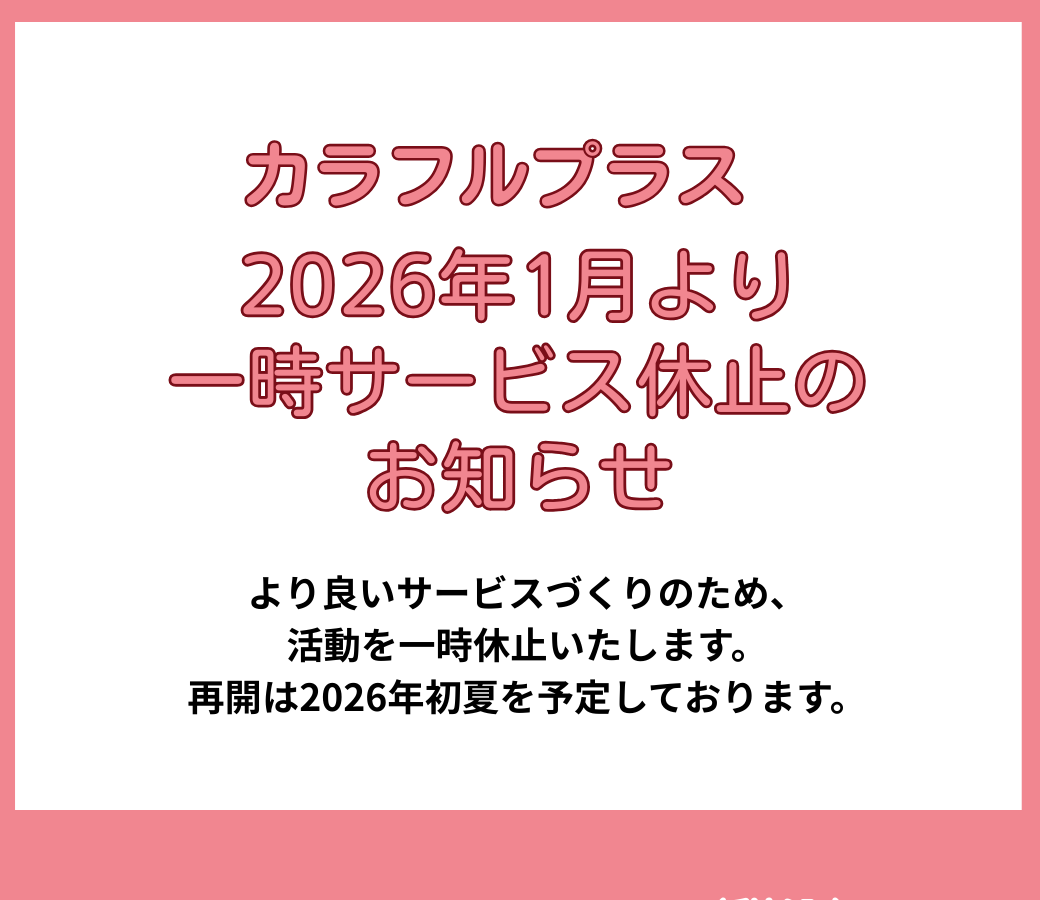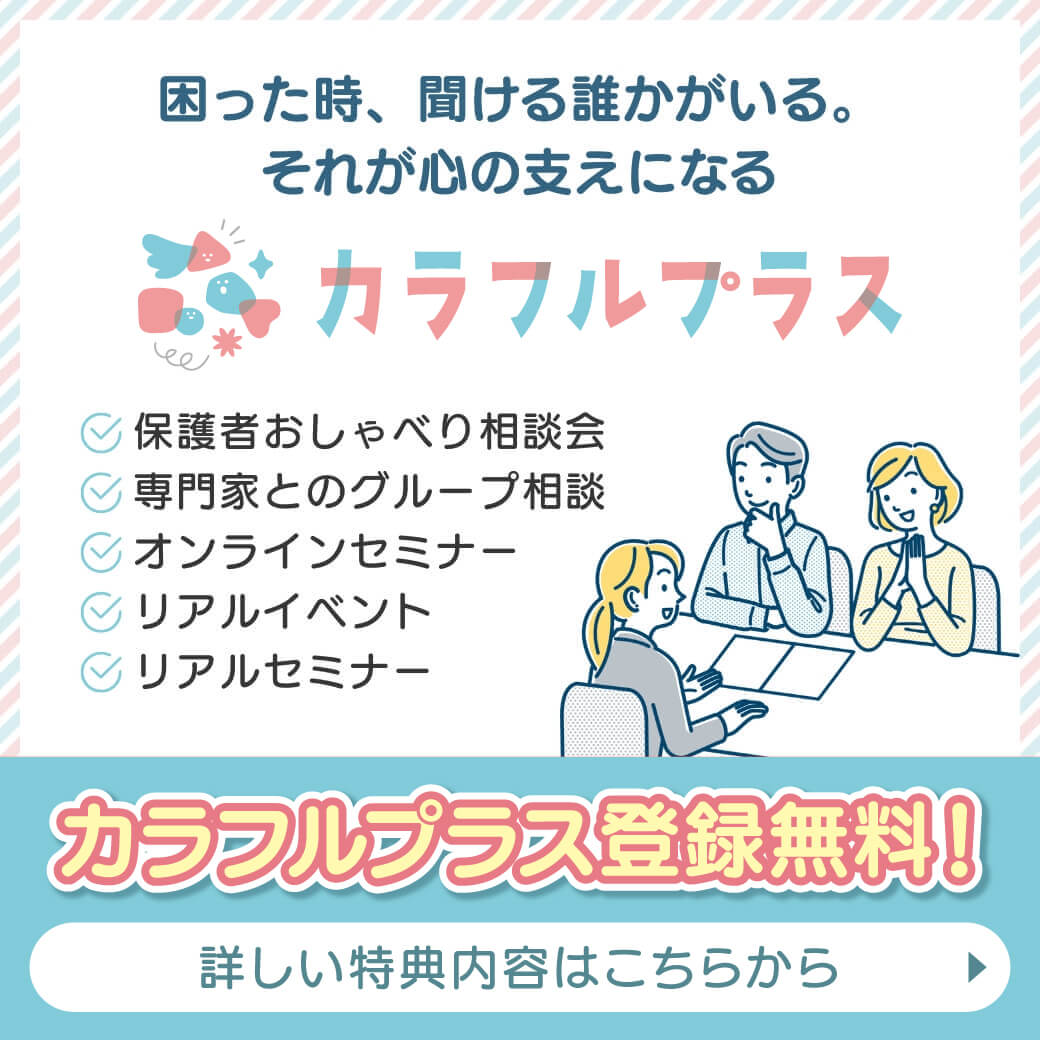前編では、「温度(温覚・冷覚)」「におい(嗅覚)」「触れた感じ(触覚)」にスポットライトを当てて、お子さんの偏食について、理由や工夫をお伝えしました。
後編では、「見た目(視覚)」と「噛む感覚(固有覚)」、「口の中で感じる圧迫感(圧覚)」についてお伝えします。
見た目(視覚)に過敏なお子さんの場合
といった様子が見られるときは、色に対する感覚がとても敏感なのかもしれません。
このような場合は、焼き色をつけて色を変えたり、見た目が目立たないようにすることで、口にできるきっかけになることがあります。
調理の様子を一緒に見たり、手伝ってもらったりすることで、「これなら大丈夫かも」という気持ちが生まれることもあります。
嚙む感覚(固有覚)が鈍いお子さんの場合
という場合、噛む感覚が分かりにくいことがあります。
このようなお子さんは、しっかり噛めるものや噛みごたえのある食感を好むことがあります。
はじめは揚げ物のように噛みごたえのあるものから始めて、ムニエル→焼き物→煮物と少しずつ柔らかいものに慣れていけるようなステップが踏めると、無理なく食べられるものの幅が広がっていきます。
圧迫感(圧覚)に敏感なお子さんの場合
―こんな様子が見られる場合は、食べ物が口や喉に入るときの感覚がつらいのかもしれません。
具材を小さく切って、圧迫感をやわらげてあげると、食べることへの抵抗感が少なくなることがあります。
今回のまとめ
偏食は感覚の問題以外にも、「これがいい」「これは嫌」といったこだわりや不安、そして食事をする環境など、色々な理由が関係していることがあります。
でも、その子にあった方法を少しずつ探っていくことで、「食べられた!」という小さな成功体験が積み重なっていきます。
ご家庭での食事の時間が、ほっとできるあたたかなひとときになりますように。
お子さんの「食べられた!」がひとつでも増えていきますように。