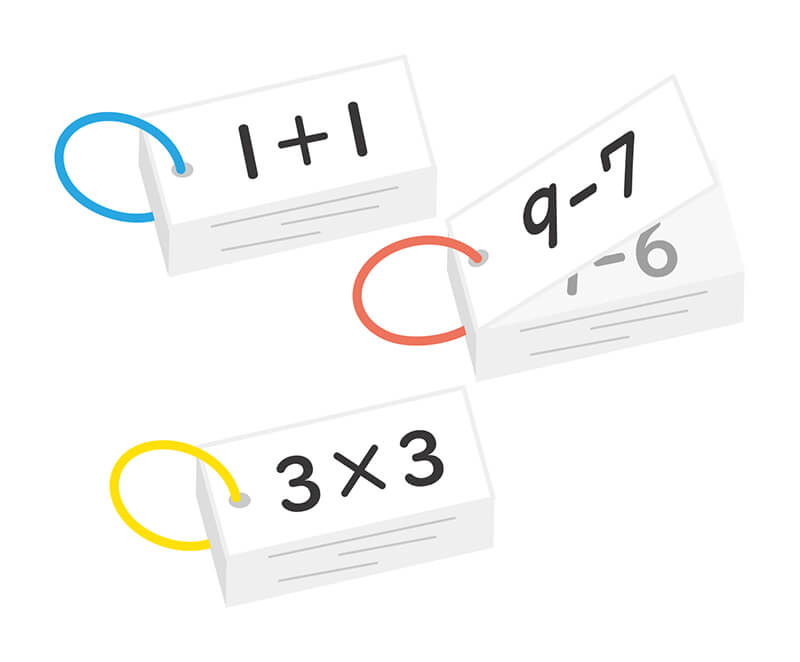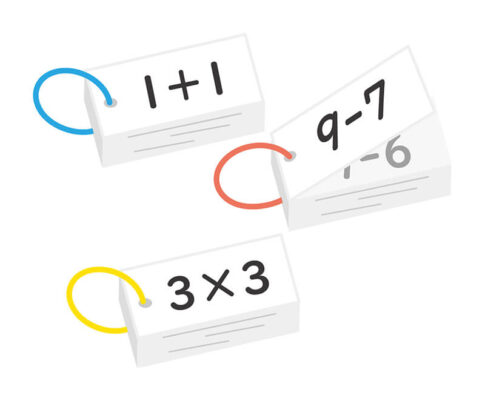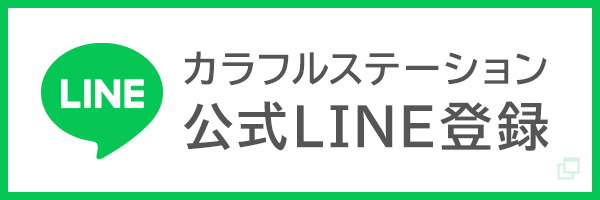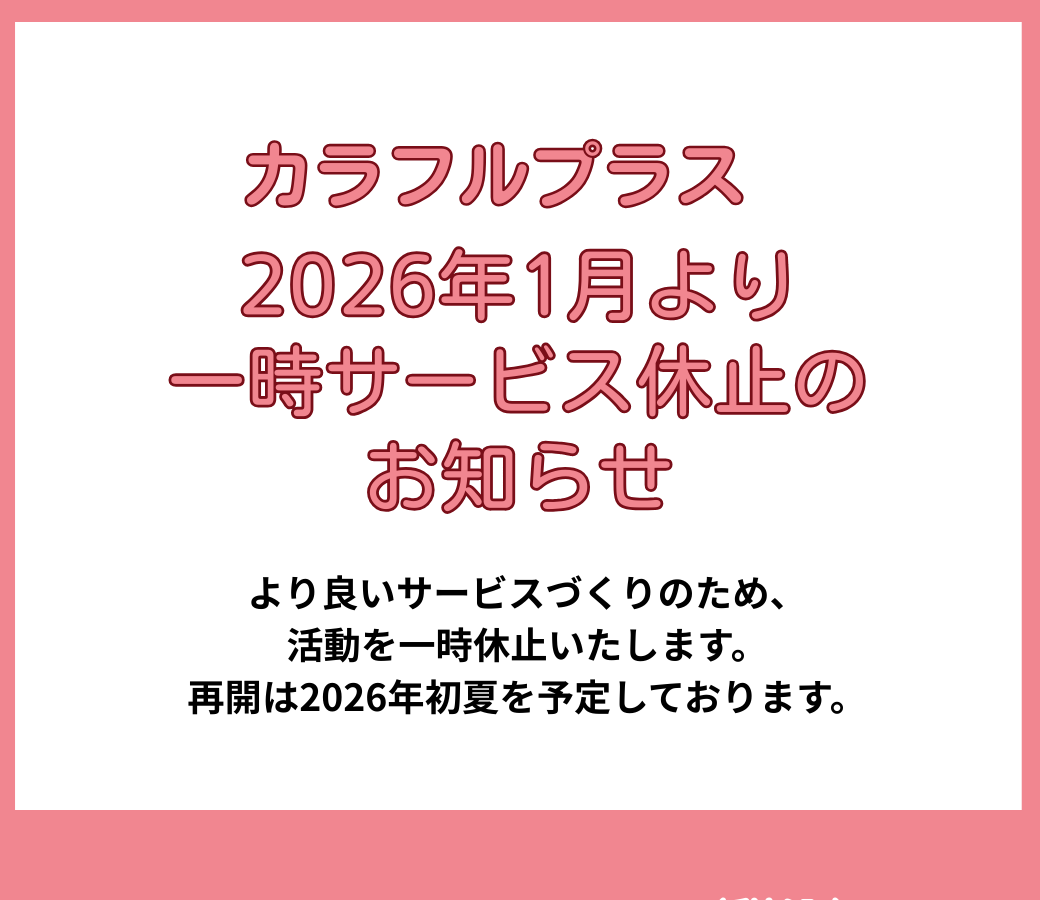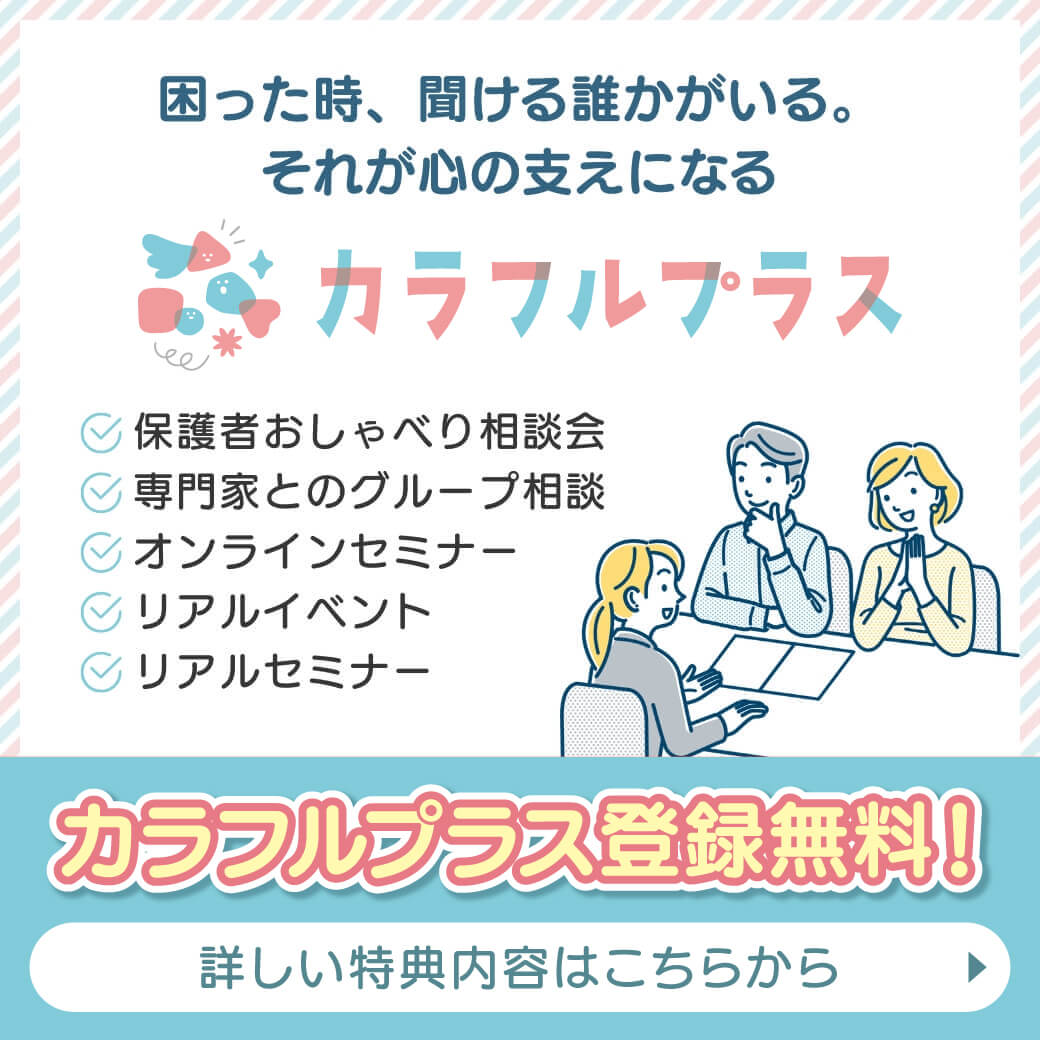「先生!音読のあとに計算カード…毎晩ヘトヘト」
そんな声を、特に共働きのご家庭から多く聞きます。
低学年の宿題でよく出される“計算カード”は、足し算・引き算・かけ算の答えをテンポよく唱える練習です。
ただ子ども一人でなんとなくやってしまい、間違った答えを覚えてしまうケースもあります。
夕方の忙しい時間帯は、宿題に時間がかかり、親にとって大きな負担になりがちです。
計算に大切なのは“量の感覚”
まず知っておいてほしいのは、低学年で習う足し算や引き算、かけ算の本質は、“量のやりとり”や“まとまりの数”を理解することです。
たとえば、「3+2」は「3つのものと2つのものを合わせると、いくつ?」というイメージがもてているかどうか。
計算カードに取り組む前に抽象的な“量の感覚”がまず育っているかを確認することが大切です。
計算カードの目的は“暗記とスピード練習”
計算カードの目的は、量の感覚が育ったうえで“計算をスムーズに解ける力”を暗記によって定着させることにあります。
なぜスピードが大切かというと、4年生以降の「分数」「小数」「面積」などの学習では、基本の計算がスムーズにできることが土台になるからです。
中学・高校でも、「5+7=12」や「6×7=42」と瞬時に答えられる力はとても重要です。
スピードを高めるための練習は「量の意味を理解しているか」を大人が確認しながら取り組むのがおすすめです。
楽しく続けるための工夫
最後に伝えたいこと
「うちの子、全然やる気がなくて」と感じても、やる気だけの問題とは限りません。
処理に時間がかかるタイプの子や、視線の動かし方が苦手な子もいます。
また、量の感覚がわからないことで、計算を苦痛に感じる子もいるのです。
子どもに合ったやり方を少しずつ、一緒に探していくことが大切です。
そして、「私が頑張りすぎなくていい」と、どうかご自身を責めずにいてください。
学び方は一人ひとり違っていい。
お子さんが楽しく力を伸ばしていけるように、一緒に合った方法を見つけていきましょう。