子どもの言葉の遅れや落ち着きのなさなど、発達面で気になることがあると、「どこに相談すれば?」「病院に行くべき?」と迷ってしまう保護者の方は少なくありません。
ここでは、医療機関で受けられる主な支援や、受診の前に知っておきたい準備や心構えを分かりやすくご紹介します。
医療機関ではどんな支援が受けられるの?
強い不安やイライラ、腹痛などの症状がある場合には、医師が薬の処方を検討することもあります。
薬は発達特性そのものをなくすものではなく、生活しづらさを和らげるためのひとつの手段です。
病院によっては、医師のほかに心理士や言語聴覚士、作業療法士などが在籍しており、発達検査やカウンセリング、言語発達の支援など、それぞれの専門性を活かした支援が受けられることもあります。
ただし、園や学校と連携して支援することが非常に大切です。
医療だけでは対応が難しい場面もあるため、連携をしてもらえるよう申し出ることも、ときに必要です。
受診を決めたら―事前準備と心構え
強い不安やイライラなどの精神症状が見られる場合は児童精神科、子どもが比較的低年齢で、言葉の遅れや身体の使い方にぎこちなさなどがある場合、小児科の発達外来への受診を検討しましょう。
どこを受診すればよいか迷ったら、自治体の子育て支援窓口などで相談するのもおすすめです。
初診まで数ヶ月待つこともあるため、早めの予約が肝心です。
もし不眠や腹痛などの症状が強い場合は、かかりつけの小児科で一時的に相談するのもひとつの方法です。
受診時には、母子手帳、保険証、子ども医療証などを持参しましょう。
可能であれば、園や学校の先生に、集団生活での子どもの様子を書いてもらうと診察時に役に立ちます。
子どもには「これからもっと過ごしやすくなる方法を考えるために先生とお話するよ」と、前向きな声かけをしてあげてください。
また保護者自身も「完璧に説明しよう」と構えすぎず、日々の様子を率直に伝えることが大切です。
まとめ
「診断」や「薬」と聞くと不安を感じるかもしれませんが、これらはあくまで子どもが安心して過ごすための支援のひとつです。
家庭、園、学校、医療が連携しながら、その子らしく育っていける環境を整えていくことが重要です。
(参考文献)
・滝川一廣(2017)子どものための精神医学 医学書院
・浜内彩乃(2024)流れと対応がチャートでわかる!子どもと大人の福祉制度の歩き方 ソシム株式会社
・岡田俊(2022)親の疑問に答える 子どものこころの薬ガイド 日本評論社
・横山北斗(2022)15歳からの社会保障-人生のピンチに備えて知っておこう! 日本評論社







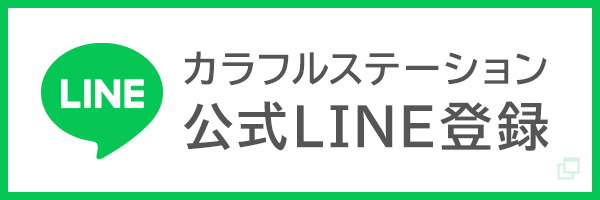
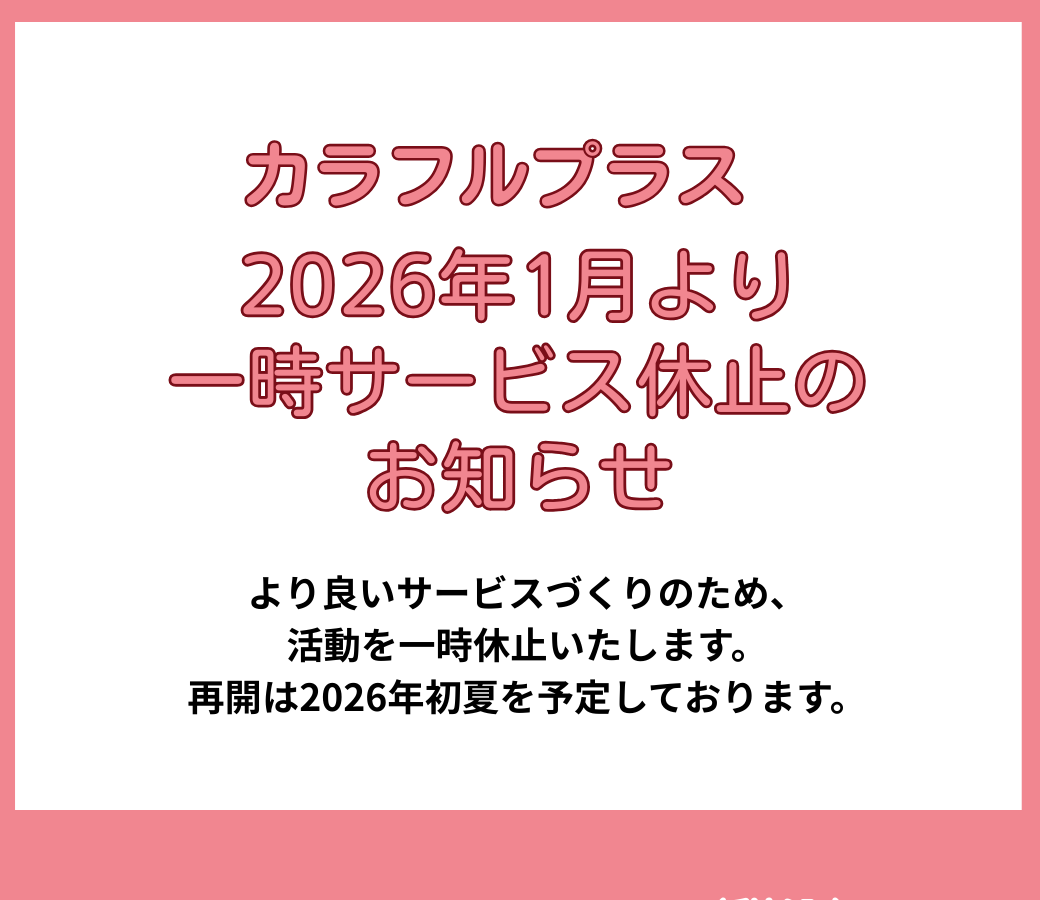





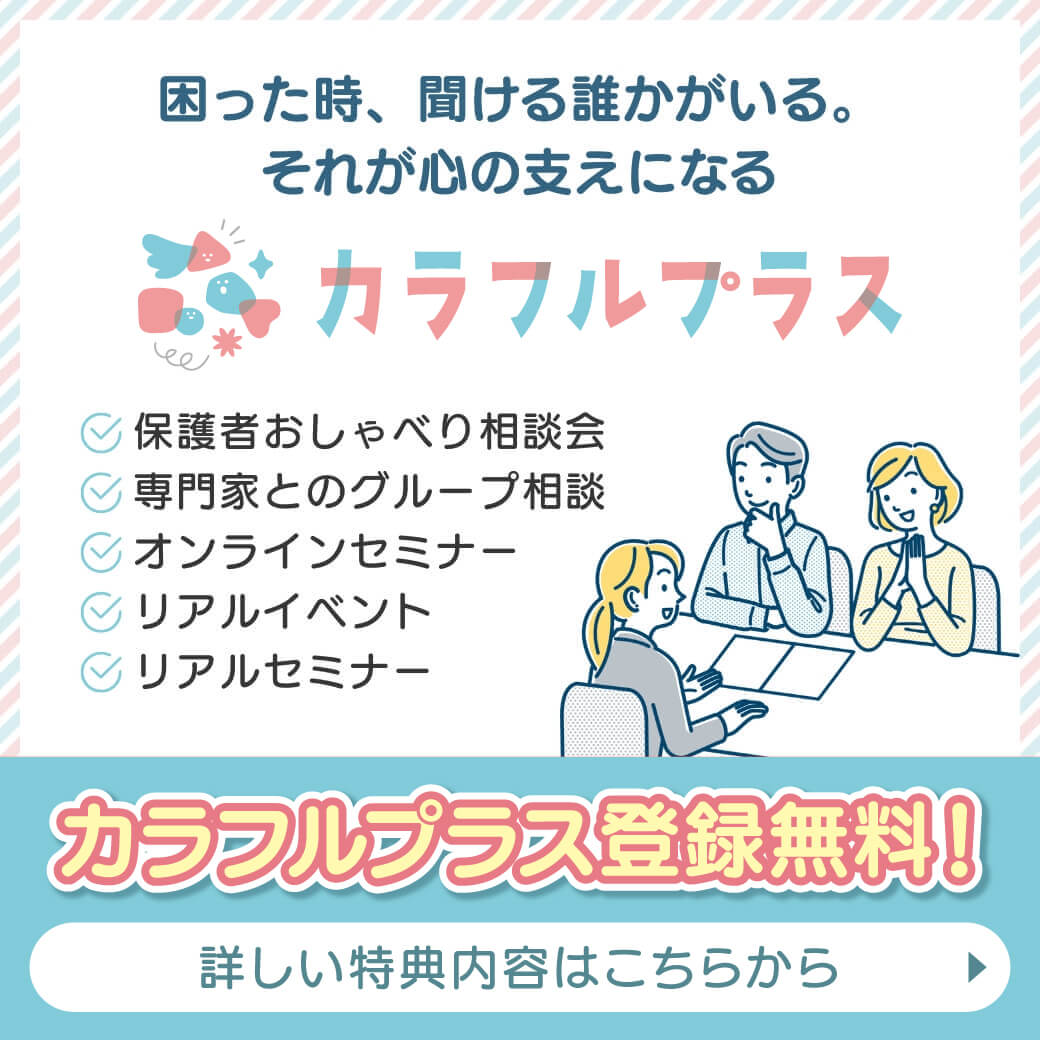
診断がつくことで、行政の福祉サービスや園・学校での合理的配慮が受けやすくなります。
診断は子どもを「決めつけるもの」ではなく、その子に合った支援を見つけるための出発点です。
医師からの説明は、可能な限り家族で一緒に聞くと理解が深まりやすいでしょう。