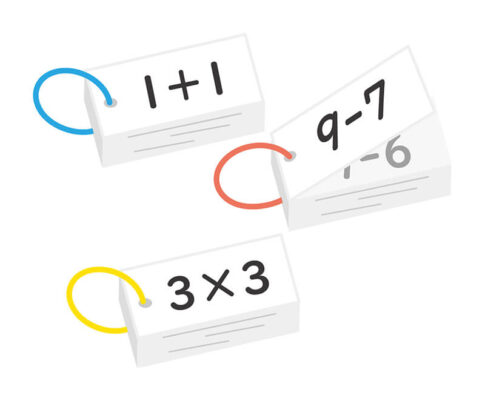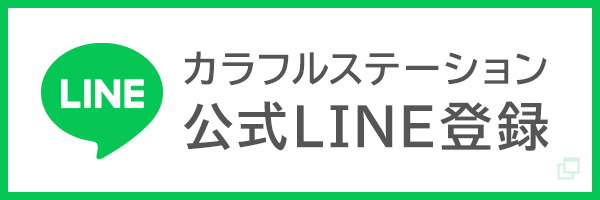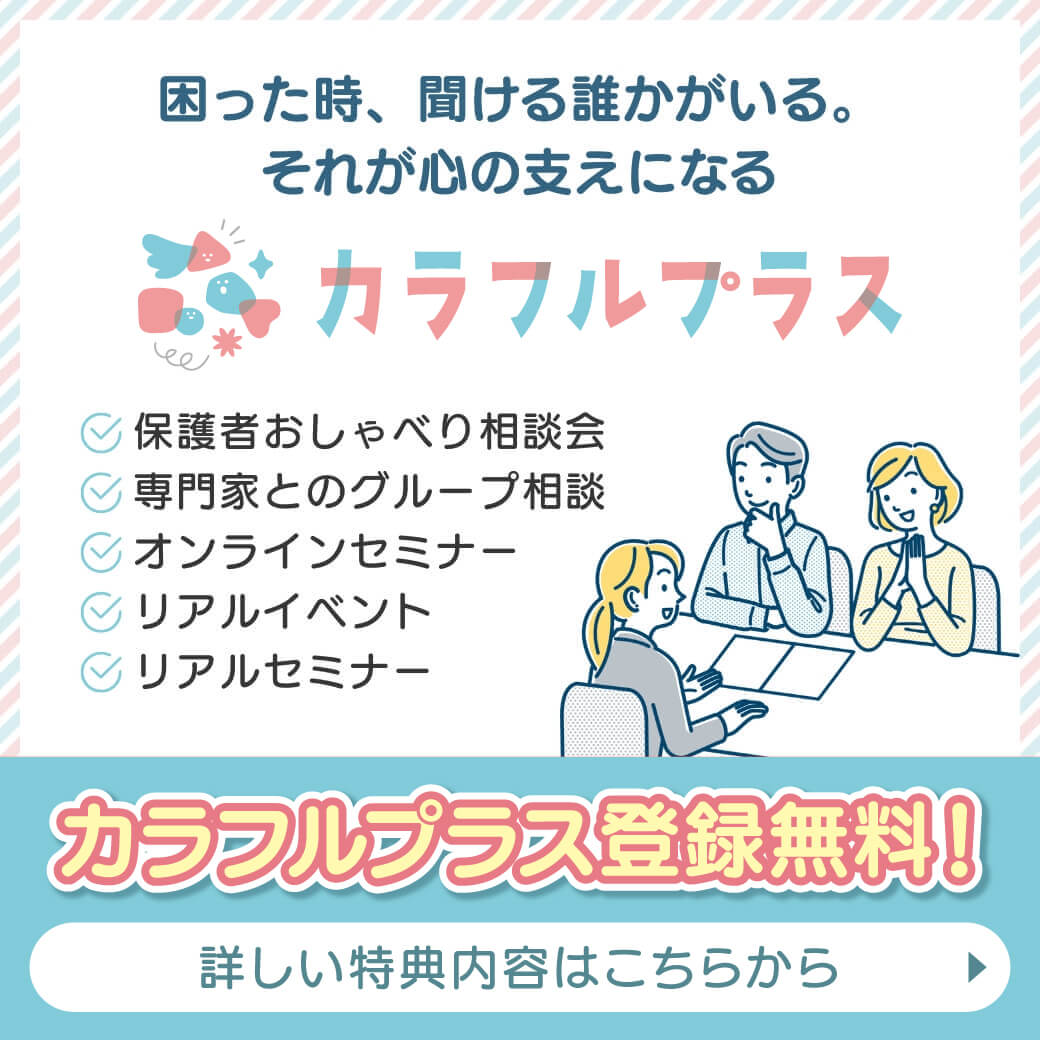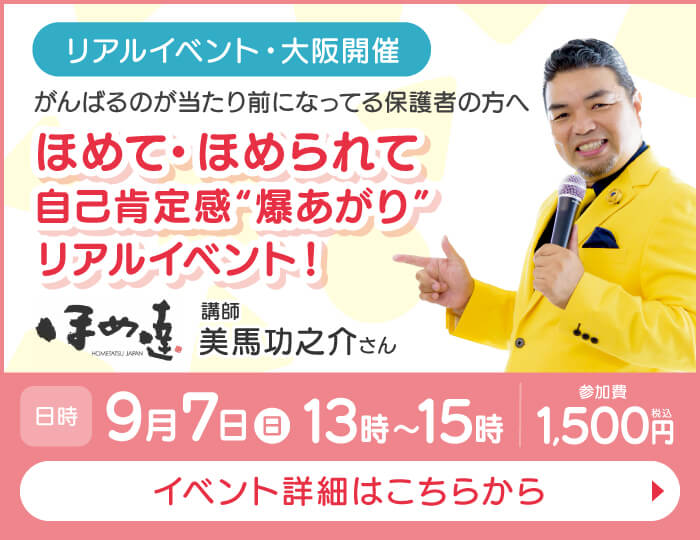目次
「伝えているのに動かない」には理由がある
そんな悩み、よくわかります。
でも実は、子どもはわざと無視しているわけではありません。伝え方を少し変えるだけで、子どもがぐんと動きやすくなることがあります。
今日は、元小学校教諭の私が現場で成果を実感してきた「子どもに伝わる指示」のコツをご紹介します。
今日から使える!具体的な声掛けのコツ5選(場面別フレーズ付き)
「否定」をやめて、「肯定」+「見通し」を伝える
やってほしい行動を具体名で示し、先の見通しを添えると動き出しやすくなります。
子どもの特性を理解し、興味を味方につける
注意の切り替えや動機づけは、外部からのきっかけと子どもの関心を結びつけることでうまくいきます。
アイ(I)メッセージでやさしく伝える
子どもの防衛反応が起きにくく、受け入れやすくなります。
対等な目線で、子どもを尊重する
自己決定感があるほど、行動は続きやすくなります。
理由とご褒美をセットでシンプルに伝える
理由は納得を促し、ご褒美は行動のスイッチになります。説明は短くが鉄則です。
+α(アルファ)の「感謝・ほめ言葉」で子どもの心を動かす
- 「できたね!」
- 「さすがだね!」
- 「ありがとう!」
- 「助かったよ!」
「できる」を引き出す伝え方をしよう
子どもが動きやすくなるかどうかは、指示の出し方ひとつで大きく変わります。
「否定」から「肯定」へ、「命令」から「尊重」へ──。
具体的で分かりやすい指示は、子どもの「できる」を引き出します。
まずは今日から
このフレーズを毎日の生活に取り入れてみてください。子どもも大人も無理せずに、笑顔で日々を過ごせますように。
応援しています!